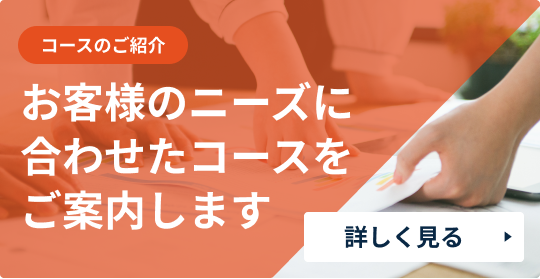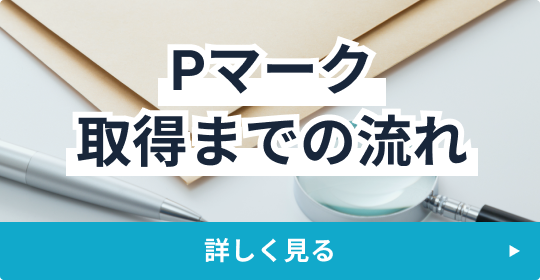INFORMATION
お役立ち情報
2025.05.04
テレアポ中に「個人情報の目的外利用だ!」と怒鳴られた新人・田中くんの奮闘記〜情報漏えいと誤解されない営業の心得とは〜

「君!この電話、どういうつもりだ!うちはそんな情報を渡した覚えはないぞ。これは“目的外利用”じゃないのか!?個人情報を勝手に使ってるんじゃないのか!?」
4月のある昼下がり。
新卒でBtoB商材を扱う営業会社「A社」に入社したばかりの田中悠真(たなか ゆうま)(仮名)は、電話の向こうから聞こえてきた怒声に固まっていた。
社会人になって、まだ2週間。電話営業(いわゆるテレアポ)に配属され、リストに従って一件ずつ架電を始めた矢先だった。
まさか、**「個人情報の目的外利用だ!」**と怒鳴られるなんて思ってもいなかった。
受話器を置いた後、田中くんは手が震えていた。
先輩社員の水野さんに事情を話すと、苦笑しながらこう言った。
「それ、初テレアポあるあるだよ。大丈夫、君が違法行為をしたわけじゃない。でも、確かに“伝え方”にはコツがある」
田中くんは、混乱していた。自分は上司から渡された“リスト”をもとに電話をしていただけ。企業向けのツール紹介をしていただけ。なのに、なぜ「個人情報を勝手に使うな」と言われるのか。
水野さんは、田中くんのノートを開いて説明を始めた。
「まず、“目的外利用”って何かというとね、個人情報保護法で定められているルールのひとつなんだ。簡単に言えば、『この情報はこの目的で使います』って本人に説明して集めた情報を、別の目的で勝手に使っちゃいけないってこと」
「なるほど……でも僕ら、個人のスマホとかにかけてないですよ?会社の代表番号にかけてるだけです」
「そう、それが大事なポイント。個人情報か法人情報かってのは大きな分かれ目なんだ」
水野さんは続けた。
「会社名・代表電話番号・代表者名などは、基本的には“個人情報”ではない。つまり、営業電話をかけるだけで即、違法になることはない。
だけど、かけ方や話し方を間違えると、“うちの情報が勝手に使われている”と誤解されてしまう」
水野さんは、ホワイトボードにこう書いた。
例:「〇〇の業界名簿から貴社を拝見し、ご連絡いたしました」
→「どこでうちの情報を得たの?」という疑問を封じる。
✅法人向けであることをはっきり伝える
例:「個人様ではなく、御社の営業ご担当者様へご案内しております」
→「個人情報を勝手に使われた」との誤解を防ぐ。✅自社の社名・目的・商品名を明確に伝える
例:「株式会社〇〇の田中と申します。新しい業務管理ツールのご紹介でお電話しました」
→「怪しい」「誰なのか分からない」という拒絶を避ける。
✅相手の意向を尊重し、無理に話を進めない
例:「ご不要であれば、今後ご案内を控えさせていただきます」
→クレーム予防と信頼構築に効果大。
✅記録と管理体制を整える
→リストの出所・使用目的・使用範囲を社内で明確にしておくことで、万が一の問い合わせにも対応できる。
「テレアポって、うまくやれば信頼される第一歩になる。でも、油断すれば“うさんくさい”“不快”に変わる。
だからこそ、“情報の使い方を意識すること”は、営業の基本姿勢でもあるんだよ」
水野さんの言葉は、田中くんに深く刺さった。
「テレアポは怖くない。ただし、誠実であれ。情報の持ち主に対して、正直で、丁寧であれ――」
翌週、田中くんは再び架電を始めた。今度は、「どこで得たか」「なぜかけているか」「どこに属する者か」を一つひとつ明確にしながら。
すると、ある日。電話の向こうからこう言われた。
「きちんと説明してくれてありがとう。実は、こういう電話っていつも嫌だったけど、あなたの対応はちゃんとしてたよ。話、少し聞いてみるよ」
ほんの少し、田中くんの声が弾んだ。
佐藤さんの行動が合法かつ公益通報として認められる可能性が高いことはわかってきました。
けれども、もし彼がもう一歩違う行動をとっていたら――話はまったく別のものになっていたかもしれません。

ケース1:他人の勤怠データも一緒に持ち出していたら?
「実は、同期の村上くんも残業がひどくて。だから彼の分も一緒に持ち出してあげようと思ったんです」
――もし、佐藤さんがそんな“親切心”で他人の勤怠情報までコピーしていたら、どうなっていたでしょう?
これは明確に個人情報保護法違反となります。たとえ会社のPCに自由にアクセスできる立場だったとしても、本人の同意なく第三者の個人情報を取得・持ち出すことは違法です。罰則の対象にもなりうる、深刻な違反です。
ケース2:SNSにアップして世間に晒していたら?
「証拠としてSNSで公開した方が話題になるかなと思って、画像をツイートしました」
――これも非常に危険です。
公益通報としての保護が成立するのは、**「正当な通報先に対して」「通報する目的で行われた場合」**に限られます。SNSへの公開は、企業名や個人名を晒す行為となり、名誉毀損罪や信用毀損罪、プライバシー侵害など複数のリスクを伴います。
企業側から名誉毀損による損害賠償請求をされることも十分にあり得ます。
ケース3:社内で禁止されていた方法で情報を抜いたら?
たとえば会社が「外部USB使用禁止」「勤怠データの印刷持ち出し禁止」と明記していたにもかかわらず、それを破って情報を持ち出した場合。
この場合、たとえ持ち出したのが自分の情報だけだったとしても、社内規定違反に該当します。
在職中なら懲戒処分、退職後であっても民事上の債務不履行や秘密保持義務違反として追及されるリスクがあります。
ケース4:勤怠情報に他の機密が混じっていたら?
「自分の勤怠表の備考欄に、どのプロジェクトに関わっていたかや、取引先名が記載されていました」
このような場合、勤怠データの中に業務機密や顧客情報が混ざっているケースもあります。これは、不正競争防止法違反のリスクが生じる可能性があります。
特に営業機密や取引先との契約条件などが紐づいていると、単なる“自分のデータ”という枠を超えてしまうため、取り扱いには細心の注意が必要です。
佐藤さんが違法とならなかったのは、「自分の情報だけを」「適切な方法で」「適切な機関に」「公益目的で」提供したからです。
逆に、たとえ同じ勤怠データであっても、使い方や送り先、そこに含まれる情報によって、法的な意味合いがまったく変わってしまうのです。
「じゃあ、怖くて何もできないじゃないか」――そう思った方もいるかもしれません。でも、違法かどうかのポイントを押さえ、誠実な姿勢で行動すれば、正当な通報者として守られる仕組みは、日本の法律の中にちゃんと存在します。
大切なのは、情報を「味方」にすること。
佐藤さんのように、自分の働き方に疑問を持ち、声を上げることを恐れず、その一方で法律やルールを学び、冷静に一歩踏み出す――
それが、本当の意味で「正しい告発」といえるのではないでしょうか。

情報は力です。
営業リストも、電話番号も、担当者名も、それを扱う人の“姿勢”によって武器にも、爆弾にもなります。
目的外利用かどうかは、単に法律の話ではありません。相手が「自分の情報が勝手に使われた」と感じれば、それはすでに信頼の喪失です。
逆に、丁寧に説明し、納得感を与えることができれば、それは「誠実な会社だな」という第一印象につながります。
新人営業マン・田中くんのように、一つひとつの情報に向き合い、敬意を持って使う姿勢こそが、これからのテレアポに求められる倫理なのかもしれません。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能