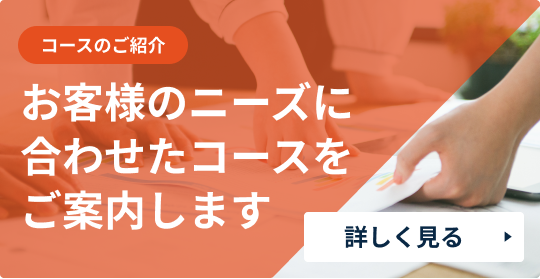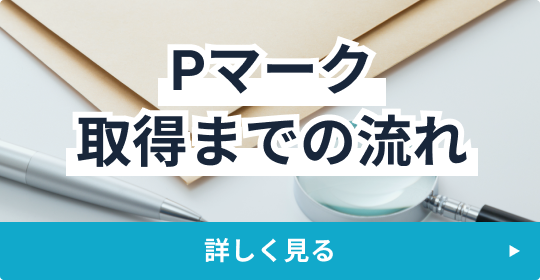INFORMATION
お役立ち情報
2025.05.05
【2025年最新版】医療業界における個人情報保護の取り組みと最新事例

2025年現在、日本の医療業界では個人情報保護の重要性がますます高まっています。
特に、電子カルテやオンライン診療の普及、AI技術の導入などにより、患者の個人情報を適切に管理・活用することが求められています。
本記事では、最新の法改正や実際の事例を交えながら、医療業界における個人情報保護の取り組みをご紹介します。
日本の個人情報保護法は、3年ごとに見直しが行われており、2025年にも改正が予定されています。
今回の改正では、医療分野における個人情報の取り扱いに関して、以下のようなポイントが注目されています。
1-1. 仮名加工医療情報の利活用
2024年4月に施行された改正次世代医療基盤法では、仮名加工医療情報の利活用が新たに認められました。これにより、個人を特定できない形での医療データの活用が可能となり、研究や公衆衛生の向上に寄与しています。
1-2. 同意取得の見直し
従来、医療データの利用には患者の同意が必要とされていましたが、改正法では、統計作成やAI開発など特定の目的に限り、同意なしでのデータ利用が可能となる場合があります。これにより、医療分野でのデータ活用が促進されることが期待されています。
医療機関では、患者の個人情報を守るために、さまざまなセキュリティ対策が講じられています。厚生労働省が公表している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(5.1版)」では、以下のような対策が推奨されています。
2-1. アクセス権限の管理
電子カルテやネットワーク機器へのアクセス権限を適切に設定し、必要最小限の職員のみがアクセスできるようにすることで、情報漏洩のリスクを低減します。
2-2. インシデント対応体制の整備
情報漏洩や不正アクセスなどのインシデントが発生した場合に備え、迅速な対応ができる体制を整備することが求められています。
2-3. 職員教育の実施
医療機関の職員に対して、個人情報保護やセキュリティに関する教育・訓練を定期的に実施し、意識の向上を図ります。
2025年には、医療機関における個人情報の取り扱いに関する事例がいくつか報告されています。これらの事例から、個人情報保護の重要性を再認識することができます。
3-1. 近畿大学病院での患者情報の誤配布
近畿大学病院では、患者支援センターにおいて、11名の患者情報が記載された書類が誤って院内のリーフレットラックに配架される事案が発生しました。このようなヒューマンエラーによる情報漏洩は、日常的な業務の中でも起こり得るため、職員の意識向上と業務プロセスの見直しが必要です。
3-2. 職員のSNSによる患者情報の漏洩
ある医療機関では、職員が業務時間外に私的なSNSアカウントから患者の病状やリハビリの様子を投稿し、プライバシーの漏洩が発覚しました。このような事案では、医療機関が使用者責任を問われる可能性があるため、職員へのSNS利用に関する教育やガイドラインの整備が重要です。
医療分野では、AI技術の導入が進んでいますが、個人情報保護法がその活用の壁となる場合があります。AIは大量のデータを学習する必要がありますが、個人情報の削除義務や匿名加工の制限があるため、活用が難しいケースもあります。そのため、個人からのオンライン同意取得や、匿名加工情報の活用など、新たな仕組みの整備が求められています。
医療機関が個人情報保護を強化するためには、以下のような取り組みが必要です。
最新の法令やガイドラインの把握:個人情報保護法や次世代医療基盤法など、関連する法令の最新情報を常に把握し、適切な対応を行う。
セキュリティ対策の強化:システムの脆弱性診断やペネトレーションテストを実施し、情報漏洩のリスクを低減する。
職員教育の徹底:個人情報保護に関する教育・訓練を定期的に実施し、職員の意識を高める。
患者への説明責任の履行:個人情報の取り扱いに関して、患者に対して明確な説明を行い、信頼関係を築く。
2025年の医療業界では、個人情報保護の重要性が一層高まっています。法改正や技術の進展に対応しながら、患者の信頼を得るための取り組みが求められています。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能