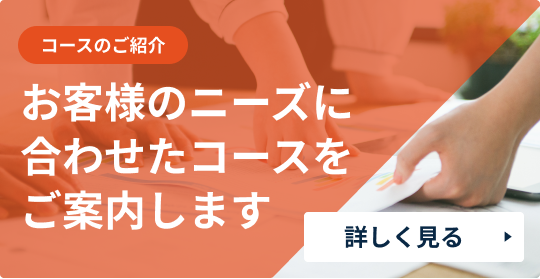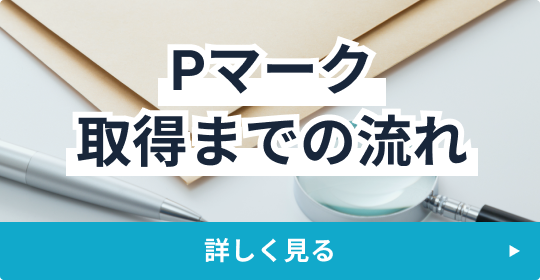INFORMATION
お役立ち情報
2025.10.23
複数当事者間での個人情報の適正な取扱いと最新の個人情報保護法改正の実務対応
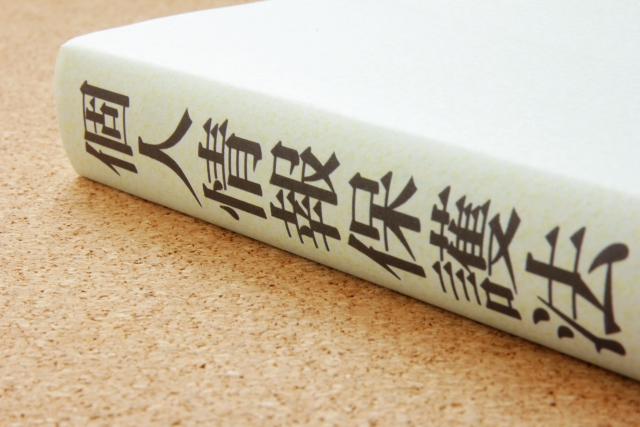
❇️はじめに
デジタル社会の進展に伴い、企業間や組織間での個人情報の共有・連携が日常的に行われるようになっています。
特にマーケティング、医療、教育、金融といった分野では、複数の事業者が協力してサービスを提供する中で、個人情報をどのように適切に扱うかが重要な課題となっています。
この記事では、複数当事者間での個人情報の利用における留意点と、個人情報保護法の最新改正動向、それに対応するための実務について詳しく解説します。
複数当事者間での個人情報の利用とは
複数当事者間での個人情報の利用とは、例えば以下のようなケースを指します。
💠 企業Aと企業Bが共同でキャンペーンを実施し、応募者情報を共有する場合
💠 医療機関と研究機関が患者情報を用いた共同研究を行う場合
💠 教育機関と自治体が生徒の進路情報を共有して支援を行う場合
このような情報の共有には、個人情報保護法に基づく正当な理由と手続きが必要です。
目的外利用の禁止、第三者提供に該当するか否かの判断、本人同意の取得方法などが重要なポイントになります。
個人情報保護法における第三者提供と共同利用
複数当事者間での情報共有が「第三者提供」に該当する場合、原則として本人の同意が必要です。
ただし、以下の「共同利用」の要件を満たす場合には、同意を得ることなく情報を共有することができます。
2. 共同利用する個人情報の項目が明確であること
3. 利用目的が特定されていること
4. 管理責任者が定められていること
これらの条件を満たさない場合は、たとえグループ会社間であっても「第三者提供」となり、適法性に問題が生じます。
2022年・2023年の法改正の主なポイント
個人情報保護法は、デジタル化の進展に対応するため、近年頻繁に改正されています。
特に2022年と2023年の改正では以下の点が注目されました。
✅ 不適正な利用の禁止の明文化
✅ 仮名加工情報・匿名加工情報の制度強化
✅ オプトアウト提供の厳格化
✅ 外国にある第三者への提供に関する説明責任の強化
これにより、企業は情報の取り扱いにおいてより明確なルールと高い透明性が求められるようになりました。
複数当事者間での利用においても、これらの法的要件を踏まえた実務対応が求められます。
実務上の対応ポイント
以下は、複数当事者間で個人情報を取り扱う際に企業が取るべき主な対応策です。
2. プライバシーポリシーの更新:共同利用に関する記載を明記し、誰が責任者かを示す。
3. 社内教育の強化:個人情報の取扱いに関する研修を定期的に実施。
4. 監査とログ管理:共有情報の利用状況を監査し、アクセスログを記録する。
5. 情報提供時の本人通知:第三者提供に該当する場合は、明確な同意取得または通知を実施。
まとめ
複数当事者間における個人情報の適正な利用は、今後ますます重要性を増していくテーマです。
企業は、共同利用や第三者提供の違いを理解し、個人情報保護法の改正に対応した社内体制を構築することが求められます。
法的なリスクを避けるためにも、実務面での具体的な対応策を講じておくことが不可欠です。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能