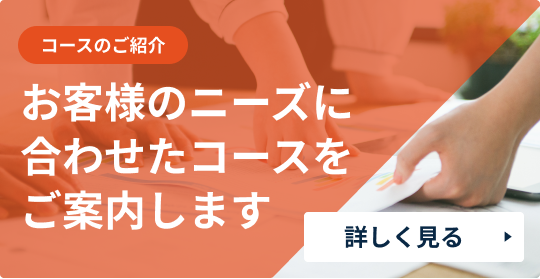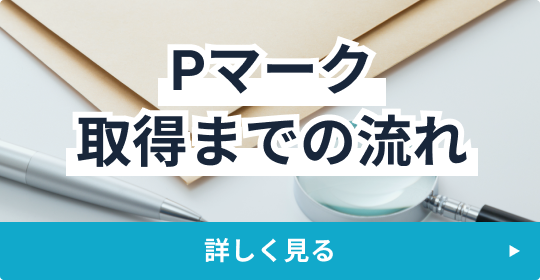INFORMATION
お役立ち情報
-

2024.09.07
匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報の違いとその重要性
個人情報保護法の改正に伴い、「匿名加工情報」「仮名加工情報」「個人関連情報」という3つの概念が注目されています。これらは、企業が個人情報をどのように扱うかを決定づける重要な概念であり、適切に理解しておくことが必要です。今回は、それぞれの違いや活用法について分かりやすく解説します。 1. 匿名加工情報とは 匿名加工情報は、個人情報から特定の個人を識別できる情報を削除し、他の情報と照合しても個人を特定できないように加工された情報のことを指します。匿名加工情報は、個人を特定できないため、法律上「個人情報」とはみなされず、比較的自由に利用・提供することが可能です。 ただし、匿名加工情報を作成する際には、元の個人情報と加工後の情報を結びつけることができないように十分な配慮が必要です。また、匿名加工情報を第三者に提供する際には、その情報が匿名加工されていることを明示する義務があります。これにより、個人のプライバシーが保護されつつ、データの活用が促進されるというメリットがあります。 2. 仮名加工情報とは 仮名加工情報は、個人情報のうち特定の個人を識別できる部分を、別の仮名に置き換えることで、すぐに個人を特定できないように加工された情報です。この情報は、他のデータと照合することで個人を再識別できるため、個人情報保護法上「個人情報」として扱われますが、一般の個人情報よりも規制が緩和されています。 仮名加工情報の特徴は、個人を識別しにくくする一方で、元の個人情報に戻すことができるため、内部でのデータ分析や業務効率化に利用しやすい点です。例えば、マーケティングの分析や統計データを処理する際に利用されることが多く、個人のプライバシーをある程度保護しつつも、企業の内部活用に役立てることができます。 仮名加工情報を使用する際には、本人の同意が不要であるため、比較的スムーズにデータを活用できますが、第三者提供や外部での利用には制限があります。また、元の情報に戻すことができるため、その取り扱いには慎重を期す必要があります。 3. 個人関連情報とは 個人関連情報は、個人を特定できる情報ではないものの、他の情報と照合することで個人が特定できる情報を指します。例えば、クッキー(Cookie)や端末の識別子などがこれに当たります。 個人関連情報自体では個人を特定できませんが、企業が他の個人情報と結びつけることで特定の個人と紐づけることが可能です。そのため、個人関連情報を第三者に提供する場合、受け手がその情報を使って個人を特定できる場合には、提供元がその事実を本人に通知したり、同意を得たりする必要があります。 個人関連情報は、オンライン広告やウェブサイトの分析など、インターネットを通じたサービス提供において広く利用されています。企業は、この情報を活用することで、ユーザーに合わせたパーソナライズされた体験を提供できる一方で、個人を特定することができるというリスクを考慮し、適切な管理が求められます。 まとめ 匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報は、それぞれ異なる特性を持ち、企業が個人情報をどのように活用できるかを左右します。匿名加工情報は個人を特定できないため、比較的自由に利用できますが、仮名加工情報や個人関連情報は、個人が特定されるリスクがあるため、慎重な扱いが求められます。 個人情報を適切に保護しながら、データの利活用を進めるためには、これらの違いを正確に理解し、適切な管理を行うことが不可欠です。特に、インターネットを介したデータの活用が進む現代において、個人情報保護法に基づいた取り扱いは、企業の信頼を守るための重要なステップとなります。 これらの情報を正しく運用することで、企業はデータ活用と個人のプライバシー保護を両立させることができ、顧客との信頼関係を強化することができるでしょう。
-
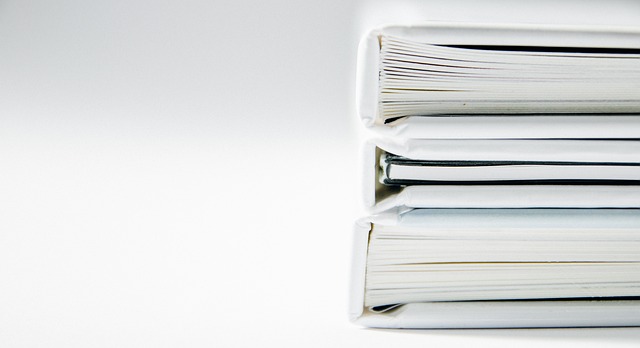
2024.09.07
個人情報保護の最新トレンドと注目すべき時事ニュース
近年、個人情報の保護に対する関心がますます高まっています。テクノロジーの進化に伴い、私たちの個人情報が多くの企業やサービスで利用される一方で、個人情報の不正利用や漏洩事件も増加しています。2023年から2024年にかけての個人情報保護に関する最新のトレンドと、注目すべき時事ニュースを解説します。 1. 改正個人情報保護法の施行 2022年4月、改正個人情報保護法が施行され、企業に対する規制がさらに強化されました。これに続き、2023年以降も個人情報保護に関連する新たなルールやガイドラインが発表されています。この改正では、個人情報をより厳格に管理し、データの取り扱いにおける透明性の確保が求められるようになっています。特に注目されるのは、「仮名加工情報」や「個人関連情報」に関する規定です。 仮名加工情報は、マーケティングなどで個人を特定せずにデータを利用する手法ですが、企業がこれを利用する際の管理体制が問われています。また、個人関連情報(クッキーや端末IDなど)に関しても、ユーザーの同意を得た上での取り扱いが求められ、無断での収集・利用に対する罰則が強化されました。 2. 個人情報漏洩事件の増加 2023年には、大手企業や行政機関における個人情報漏洩事件が相次ぎました。特に注目を集めたのは、ソーシャルエンジニアリングによるサイバー攻撃です。悪意のある第三者が巧妙な手口で企業の従業員をだまし、システムに不正アクセスして個人情報を大量に流出させる事件が多発しました。こうした攻撃手法は技術的に高度な防御策を持っていたとしても、最終的には人の不注意や不備を突かれるため、企業のセキュリティ教育の重要性が改めて浮き彫りになっています。 これを受け、企業側ではサイバーセキュリティの強化だけでなく、従業員向けのセキュリティ意識向上プログラムやフィッシング対策訓練が活発に行われています。デジタル時代において、技術的な防御とともに人間の意識改革が個人情報保護の要となっています。 3. ビッグデータと個人情報保護 もう一つの注目すべきトレンドは、ビッグデータの利活用と個人情報保護のバランスです。近年、AIや機械学習の技術が進展し、大量のデータを分析して企業の経営やマーケティングに活用する「データドリブン経営」が広がっています。しかし、こうしたデータ活用には個人情報の扱いが含まれており、特に個人を特定できる情報が含まれる場合は、慎重な対応が求められます。 2024年には、EUの一般データ保護規則(GDPR)と同様に、日本でも個人情報保護に関する規制が国際的に連携する動きが見られます。これにより、グローバルな企業は各国の個人情報保護法に準拠しながらデータを活用する必要があるため、国際的なビジネスにおいても個人情報保護の対応が重要な課題となっています。 4. 消費者のプライバシー意識の高まり 消費者の間でも、個人情報に対するプライバシー意識が高まっています。特にSNSやオンラインサービスを通じて自分の情報がどのように利用されているのかについて、透明性を求める声が強まってきました。これに応じて、企業側では利用者に対する情報開示や、データの収集・利用に関する同意取得のプロセスを見直す動きが進んでいます。 また、個人情報の削除や修正を求める「忘れられる権利」に関する議論も深まりつつあります。消費者が自分のデータに対してコントロールを持つことができる社会の実現に向けて、企業がどのように対応していくのかが今後の鍵となるでしょう。 まとめ 個人情報保護は、企業の信頼を守るための重要な要素であり、テクノロジーの進化とともにその重要性は増しています。改正個人情報保護法の施行や、個人情報漏洩事件の増加に対する企業の対応、さらには消費者のプライバシー意識の高まりといった時事的なニュースは、今後も注目すべきテーマです。企業は、個人情報保護を徹底しつつ、データ活用のバランスを取りながら、信頼されるビジネスを展開していくことが求められています。
-

2024.09.05
人手不足の会社が行うべき個人情報保護の5つのポイント!
現在、多くの企業が人手不足に直面しています。このような状況下であっても、個人情報の保護は最優先事項です。社員の数が限られている中で、どのようにして情報漏洩のリスクを最小限に抑え、顧客や取引先の信頼を維持するかが課題となります。今回は、人手不足の企業が個人情報保護を徹底するための具体的なポイントについてお話しします。 1. 情報保護の基本方針を明確にする まず、会社全体で情報保護に対する基本方針を明確にしましょう。これにより、全従業員が共通の認識を持つことができます。具体的には、個人情報を取り扱う際のルールや手順を定めた「個人情報保護方針」を策定し、社員全員に周知徹底することが重要です。この方針は定期的に見直し、必要に応じて更新することも忘れずに行いましょう。 2. 簡素化された業務フローの構築 人手不足の中で効率的に業務を遂行するためには、業務フローの簡素化が欠かせません。特に個人情報を取り扱う業務については、過度に複雑なプロセスを避け、誰でもスムーズに処理できるような仕組みを構築することが求められます。例えば、個人情報の収集・保管・削除のプロセスを明確化し、自動化できる部分は自動化することで、人的ミスを減らし、セキュリティリスクを低減することができます。 3. 社員教育と意識向上 個人情報保護において、社員一人ひとりの意識が重要です。特に人手不足の場合、少人数で多くの業務を担当することが多いため、全員が情報保護の重要性を理解していることが求められます。定期的な研修や情報セキュリティに関する教育を通じて、従業員の意識を高めることが不可欠です。特に、フィッシング詐欺やマルウェアへの対処法、データの取り扱いに関する具体的な知識を提供することが効果的です。 4. ITセキュリティの強化 技術的な対策も欠かせません。最新のセキュリティソフトウェアを導入し、定期的に更新することで、外部からの不正アクセスを防止することができます。また、アクセス権限の管理も重要です。社員ごとに必要な範囲でのみ個人情報にアクセスできるようにし、不要なアクセスを制限することで、内部からの情報漏洩リスクを抑えることができます。 5. 外部委託先の管理 人手不足の場合、業務の一部を外部に委託するケースもあります。この際、外部委託先が適切に個人情報を取り扱っているかどうかを確認することが重要です。委託先としっかりとした契約を結び、定期的にセキュリティ対策の実施状況を確認することで、委託先からの情報漏洩リスクを最小限に抑えることができます。 まとめ 人手不足の状況でも、個人情報保護を徹底することは企業としての信頼を維持するために不可欠です。基本方針の明確化、業務フローの簡素化、社員教育、ITセキュリティの強化、そして外部委託先の管理をしっかりと行うことで、限られたリソースの中でも情報保護を実現できます。これらのポイントを押さえ、持続可能な情報セキュリティ体制を構築していきましょう。
-
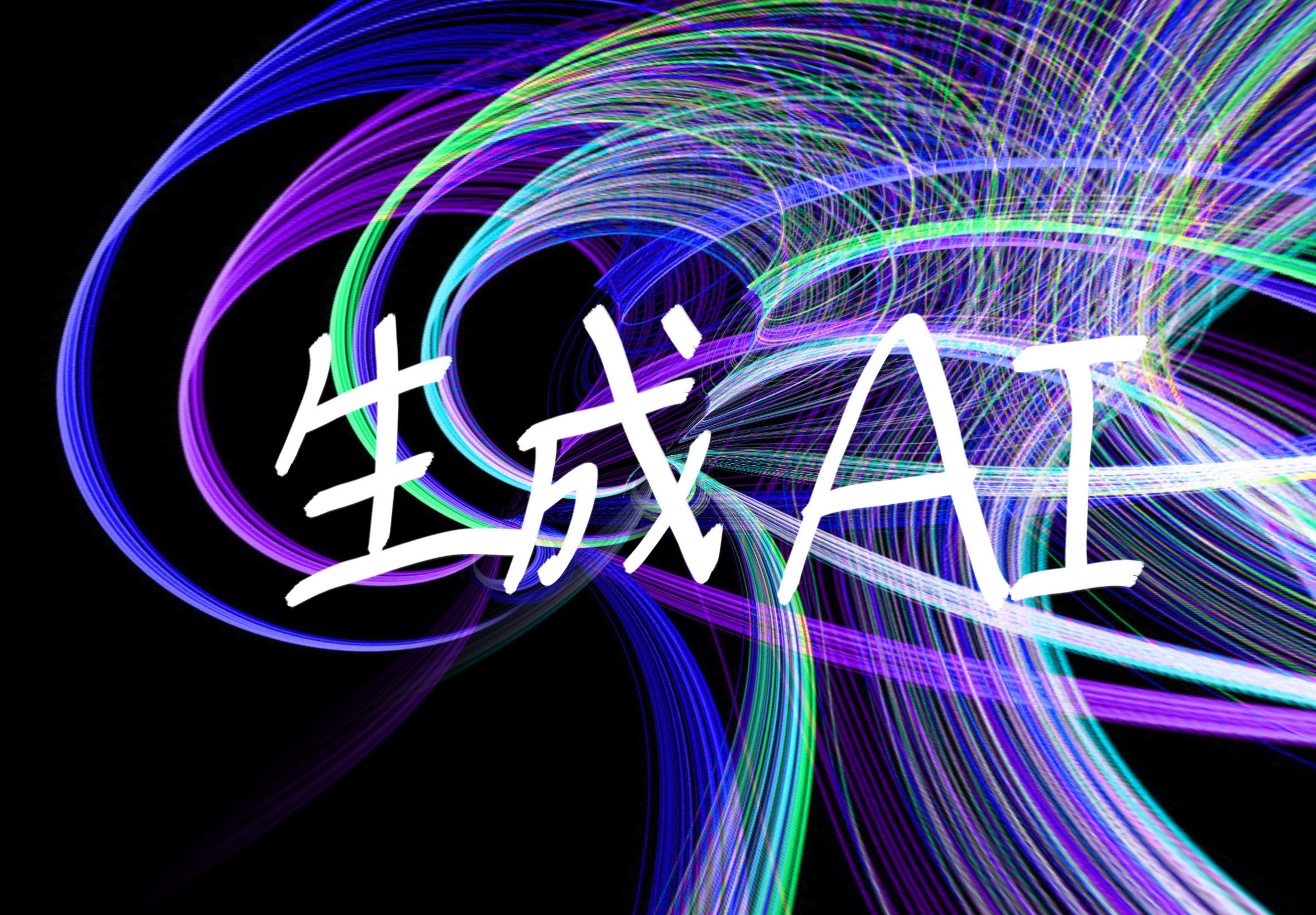
2024.01.21
「生成A I」と個人情報について
私たちの社会に急速に広がっている「AI」。 最近では飲食店の電話で予約受付を応対する「AI」がいたり、対話型チャットで色々な質問に答えてくれる「AI」がいたりと、我々の日常生活においても大変身近な存在となっています。 誰でも気軽に使える「AI」はとても便利である一方で、大きなリスクも抱えています。 例えば著作権侵害や情報の漏洩等です。 特に、大量のデータを元に文章や画像等を生成することができる「生成AI」はよりそのリスクが顕著です。 今回は、「生成AI」と個人情報について、その中に潜むリスクを主にみていきたいと思います。 とその前に、そもそも「生成AI」とは何か?をもう少し具体的にみていきましょう。 「生成AI」とは? 「生成AI」とは、与えられた大量のデータから新たなデータを生成する能力を持つ「AI」のことを言います。 従来の「AI」との違いは、オリジナルコンテンツを創造できるかどうかにあります。 「AI」は与えられたデータの中から適切なデータを探して提示するだけでしたが、「生成AI」は与えらえたデータをもとに、ゼロから新しいものを生み出すことができます。 テキストや画像、音声等のデータをもとに、新たな画像やテキストを作成するなどクリエイティブな能力を発揮することができるということです。 例えば「ChatGPT」は、与えられたテキストデータから文章を自動作成し、まるで人間と話しているように自然な会話で応対することが可能です。 一方で「生成AI」は、人間とは異なり、もとの学習データこそが全てになってしまうので、そもそものデータが誤っていた場合、自ずと生成される情報も不確実なものになってしまいます。 そこに大きなリスクが潜んでいると考えます。 今回は、様々なリスクがあるなかでも、特に個人情報についてのリスクをみていきたいと思います。 「生成AI」における個人情報流出のリスク (参照)個人情報保護委員会「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等」 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf 上記の参照にあるように、日本では個人情報委員会が「生成AI」の利用について、注意喚起を行っています。 注意喚起対象は大きく3つ、1.個人情報取扱事業者、2.行政機関等、3.一般の利用者です。 例えば、個人情報取扱事業者に対しては、「個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。」(上記参照U R Lより抜粋)とあります。 個人情報はその利用目的の範囲内で利用することがとても大切になります。 特に医療従事者や公務員等、プライバシーに関わる情報を取り扱う人たちは、充分に注意しなければなりません。 会社に属するサラリーマンも同様です。これまでに企業秘密が「生成AI」によって外部に漏れてしまった例もあります。安易に便利だからと会議の議事録作成に使用すると、それが学習データとなり多くの人に漏れてしまいかねませんので注意が必要です。 もう一つ怖いのは、「生成AI」が間違ったデータを学習してしまうことです。 個人情報保護委員会は一般の利用者に向けて、「生成AIサービスでは、入力された個人情報が、生成AIの機械学習に利用されることがあり、他の情報と統計的に結びついた上で、また、正確又は不正確な内容で、生成AIサービスから出力されるリスクがある。 そのため、生成AIサービスに個人情報を入力等する際には、このようなリスクを踏まえた上で適切に判断すること。」(上記参照U R Lより抜粋)とあります。 また、「生成AIサービスの中には、応答結果として自然な文章を出力することができるものもあるが、当該文章は確率的な相関関係に基づいて生成されるため、その応答結果には不正確な内容の個人情報が含まれるリスクがある。そのため、生成AIサービスを利用して個人情報を取り扱う際には、このようなリスクを踏まえた上で適切に判断すること。」ともあります。 我々利用者側も間違ったデータが潜んでいる可能性を踏まえて、「生成AI」を利用しなければならないということです。 まとめると、個人情報についてはむやみに「生成AI」の学習データに入力しない、また、「生成AI」の限界を知り、情報を鵜呑みにするのではなく自ら根拠や裏付けを確認することを心がけなければいけないということです。 ところで、どの入力データが「生成AI」の学習データに利用されるのかは曖昧です。 これまで以上に情報の入力自体を慎重に行っていく必要があるでしょう。
-

2023.07.27
マイナンバーカード登録のトラブルからみるリスク管理について
依然としてトラブルが相次いでいるマイナンバーカード。 公金受取口座に別の人の口座が紐付けされた問題で、個人情報保護委員会は7月19日にデジタル庁への立ち入り検査を実施しました。 他にも、医療情報や年金、銀行口座といった個人情報の漏洩も相次いでいます。 こうしたトラブルを踏まえて、個人情報保護委員会は、デジタル庁の「リスク管理及び対策ができていなかった」ことを指摘しました。 なぜミスは起こったのか? そもそも、なぜ別の人の公金受取口座が紐づけられていたのでしょうか。 全部で940件余りにものぼるようですが、こうした一連のミスは、住民の手続きを支援する自治体の窓口で起きました。 具体的には、前の登録者のログアウトが完了しないまま、次の登録者の手続きを行ってしまったことで、前の登録者のアカウントに後の登録者の口座が紐づけされてしまったことが原因のようです。 現状、このようなミスはどれだけ注意しようとも、人間がかかわっている以上起こりうる問題ではあります。 しかし、大切な情報を取り扱う以上、可能な限りこのようなミスはなくさなければいけません。 そこで重要になってくるのが、リスク管理です。 このようなミスを事前にどれだけ想定できるか、そのミスに対してどのように対応するのかを事前にしっかりと決めておくことが、とても大切になります。 個人情報保護委員会がデジタル庁に立ち入り検査したのも、デジタル庁が自治体に対して、正確なシステムの操作手順を徹底せず、リスク管理や対策を講じていなかったからでした。 ※口座の紐付けが正確にされているかを自分自身で確認する手順 ①「マイナポータル」にログイン ②「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」をクリック ③ 公金受取口座の登録状況ページを確認 もし誤りがあった場合は、登録口座をすぐに削除し、居住する市区町村に連絡してください。 個人情報保護におけるリスク管理とは (参照)プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針 https://privacymark.jp/system/guideline/pdf/pm_shishin2022.pdf では、個人情報保護におけるリスク管理の方法とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか? まずは、取り扱う全ての個人情報を特定することから始まります。 そもそも個人情報を具体的に特定できなければ、それに対するリスク管理対策もできません。 具体的には、個人情報保護管理者(個人情報を取り扱う責任者を指します)が、取り扱う個人情報を漏れなく洗い出し、それらを全て記入した台帳を作成します。 例えば以下の項目を台帳に記します。 ・個人情報の項目 ・利用目的 ・保管場所 ・保管方法 ・アクセス権を有する者 ・利用期限 ・保管期限 台帳が完成したら、社長などのトップが承認します。 この台帳は、少なくとも年一回、あるいは必要に応じて適宜に確認し、最新の状態に維持しなければなりません。 個人情報の特定ができたら、次はリスクの特定です。 各方面におけるリスクを特定し、その分析をします。 このリスク分析も多岐に渡ります。 サーバー関連から業務委託関連、人事関連に至るまで、一つ一つ細かく分析する必要があります。 このブログで取り上げたマイナンバー情報や口座情報についても、取扱いの際どのようなリスクがあるのかを分析する必要があります。 そして、それらを分析するだけでなく、一覧にしたリスク管理表を作成します。 例えば以下の項目を記します。 ・個人情報の項目 ・媒体 ・ライフサイクル(個人情報の取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等) ・リスク ・対応策 ・残留リスク(現時点では困難であるが、短期的若しくは中長期的に対応していくリスクのこと) 個人情報保護管理者は、リスク管理表を社長等のトップに提出し、承認を得ます。 そして、策定した管理策は、従業者や委託先への教育内容等に反映します。 こちらも台帳同様、少なくとも年一回、及び必要に応じて適宜に確認し、最新の状態に維持しなければいけません。 このように個人情報を保護するためのリスク管理方法は徹底して行う必要があります。 ただし、形式的なものにとどまることなく、一人一人が個人情報の保護に対して意識をしていくことこそが一番大事といえるでしょう。
-

2023.05.31
匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報、違いって何?その違い説明します!
個人情報保護法の改訂やPマークの基準が改訂され、様々な情報の種類が定義化されその線引きが難しくなってきました。また、昨今のビジネス事情からも個人情報を利用しながらも、その情報を匿名化する方法も注目されています。今回は、個人情報、個人関連情報、匿名加工情報、仮名加工情報のそれぞれの概念と、その違いについて詳しく解説します。 個人情報: 個人情報は、個別の人物を識別するための情報です。氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、銀行口座番号など、特定の個人に関連する識別可能な情報が含まれます。これらの情報は、そのままでは個人のプライバシーを侵害する可能性があるため、慎重に取り扱う必要があります。個人情報は、法的に保護され、第三者による不正アクセスや悪用から保護されるべきです。 個人関連情報: 個人関連情報は、個別の人物を直接的に識別することはできないが、他の情報と組み合わせることで特定の個人を特定できる情報です。たとえば、個人の職業、趣味、購買履歴、ウェブサイトの閲覧履歴などが個人関連情報に含まれます。単体では個人を特定することはできませんが、他の情報と組み合わせることで個人の特定が可能になるため、個人情報と同様に適切な管理が求められます。 匿名加工情報: 匿名加工情報は、個人情報や個人関連情報を匿名化するプロセスを経て生成された情報です。匿名化によって、個人を特定するための情報が削除され、一般的な統計や調査目的で利用されます。匿名加工情報は、個人のプライバシーを保護しながら、データ分析やトレンドの把握などの目的で広く利用されます。ただし、十分な匿名化が行われていない場合には、再識別が可能となり、個人情報の保護が侵害される恐れがあるため、注意が必要です。 仮名加工情報: 仮名加工情報は、個人情報や個人関連情報を、本人を識別できないように変換した情報です。匿名加工情報とは異なり、個人を特定できないように情報を加工する際に、識別子や擬似識別子(仮名)が使用されます。この方法は、個人のプライバシーを保護しながら、データの利活用や研究などに使用されます。仮名加工情報の場合、個人を再識別するためには元の個人情報にアクセスする必要があり、情報の保護が図られています。 まとめ: 個人情報、個人関連情報、匿名加工情報、仮名加工情報は、データ保護やプライバシーの観点から重要な概念です。個人情報は、直接的に個人を特定するための情報であり、慎重な管理が必要です。個人関連情報は、単体では個人を特定できないが、他の情報と組み合わせることで個人を特定できる情報です。匿名加工情報は、個人情報や個人関連情報を匿名化するプロセスを経て生成され、広範な分析や調査目的で利用されます。仮名加工情報は、個人情報や個人関連情報を本人を特定できないように変換し、データ利活用や研究に使用されます。これらの情報の適切な管理と保護は、個人のプライバシーを守るために不可欠です。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能