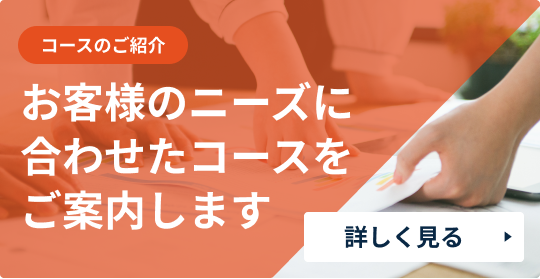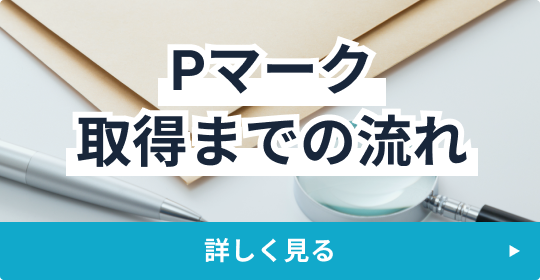INFORMATION
お役立ち情報
-

2020.12.18
悪しき慣習だった!?PPAPとは何か
皆さんPPAPという言葉をご存知ですか? 数年前に流行った歌のことではありませんよ(笑) 情報セキュリティ・個人情報保護の領域でもPPAPという言葉が存在しています。 下記の内容の頭文字を取った言葉になります。 P:パスワード付きZIP暗号化ファイルを送ります P:パスワードを送ります A:暗号化 P:プロトコル これを具体的なメールのやり取りに落とし込むと下記のような流れです。 A(メール送信者)は、添付ファイルをパスワード付きzipファイルで暗号化し、メールに添付してB(受信者)に送信する。 A(メール送信者)は、1.で送信した添付ファイルのパスワードを、別途メールにてB(受信者)に送信する。 B(受信者)には、送信者から受け取った添付ファイルとパスワードによってファイルを解凍し、添付ファイルの中身を確認する。 これまではこの形式が情報セキュリティ・個人情報保護の観点から正しいルールであると信じられてきました。 いまはこれがリスクがある行為として見直しされて来ています。 具体的にどういったことなのかを少しご紹介していきます。 【PPAP方式のリスク】 では、実際にPPAP方式を使い続けるリスクとはどんなものがあるのでしょうか。 想定されるリスクとしては下記のようなことが挙げられます。 メールを盗聴している人がzipファイルを添付したメールを入手したら、同じ手段で送られるパスワードも入手できる可能性が高い。 ●別のメールで指定されたパスワードを入力するという手間は、無駄が多い。 ●最近はファイルのzip化とパスワードの送信を自動で行っているツールが多い。手動であればパスワード送信前に誤送信に気付く可能性もあるが、児童の場合はそうも行かない。 ●添付ファイルのzip化によって、もし添付ファイルがコンピュータウイルス等に感染していたとしても、脅威に気付くことが出来ない可能性が高まる。 ●パスワード付きzipファイルのパスワード解析は、2012年時点で1秒間に45億回の試行が可能であるという報告がされている。暗号化zipファイル単体のみが攻撃者の手に渡ったとしても、中身を盗み見られる可能性は高い。暗号化の為にパスワード付きzipファイルを使う事がそもそもセキュリティ対策として有用ではない。と以前から指摘されている。 ●スマートフォン端末等では、パスワード付きzipファイルを閲覧するために専用のアプリケーションが必要となり、利便性を損なう。 ざっと例を挙げるだけでもこれだけのリスクが想定出来てしまいます。 【なぜ、利用され続けたのか】 2012年にはIPAでもPPAP方式は有用な情報セキュリティ・個人情報保護の施策として挙がっていました。 ですが、大きな理由としてはプライバシーマーク制度などの認証制度がPPAP形式を推奨し、認証上の基準として盛り込んでいたことが要因の1つだと考えられます。 認証を取得する企業は自ずとPPAP形式を利用することになってしまい、グループ会社や取引先にも広がっていった。という流れです。 【今後どうすべきか】 別の記事にも詳細を記載しているので、内容はそちらにゆずります。 ですが、今後は会社ごとに取り組むべき方式が変わってくることは事実です。 自社の規模、文化や業務上のリスクに応じた取り組みが必要になってくるため、専門家に相談・支援を受けることが効果的な取り組みだと考えます。
-

2020.11.27
好きに変えて良いの?利用目的変更の条件。
個人情報の利用目的は決まっているものと、以前の記事でも触れていますが実は法律上・プライバシーマーク上で利用目的は変更しても構わない。となっています。 ある程度具体的に利用目的を定めなければならないのに変えていいの?と疑問に思う人もいるのでないでしょうか。 ルール・制限はありますが、実のところは利用目的を変更して扱うことは違法でもルール違反でもありません。 今回は利用目的の変更に関する内容や手順について触れてみたいと思います。 【利用目的変更がOKな根拠】 そもそも、個人情報の利用目的は変更することができるのでしょうか・・・ 個人情報保護法には根拠となる条文があります。 「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」 ※個人情報保護に関する法律 15条 2項から抜粋 元々の利用目的と関連性があれば、利用目的を変更することは法律上認めています。 言い換えると本人が予想できないような、利用目的への変更は不可になります。 【利用目的の変更がOKな例】 対象:A社に勤める従業員の情報 元々の利用目的:給与計算、雇用の管理に関する手続き 変更(追加)する利用目的:A社HPでのスタッフ紹介や会社イベントの写真の掲載 【利用目的の変更がNGな例】 対象:A社に勤める従業員の情報 元々の利用目的:給与計算、雇用の管理に関する手続き 変更(追加)する利用目的:A社が新たに取り扱いを始めた美容商材のカタログを送付、会員登録 OKな例は働いている内容の紹介と言える内容となっており、利用目的変更の例としては関連性があると判断されます。 一方、NGな例は従業員の情報のサービス・事業の内容に変更する形になっているので、関連性があるとは認められない例となってきます。 【どうやって変更するの?】 では、具体的にどうやって変更するのでしょうか。 個人情報保護法では、以下のような条文があります。 16条 利用目的による制限 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ※個人情報保護に関する法律 16条 1項から抜粋 条文に記載のある通りなのですが、「あらかじめ本人の同意を得る」ことが求められています。この場合ですが、口頭の同意でもOKなのか、書面などでの同意が必要なのか。 条文上では明確な定めがありませんが、書面での同意があった方がベストだと考えられます。 【プライバシーマーク上必要な手順】 一方プライバシーマークを取得している会社で利用目的の変更を行う場合はどうでしょうか。 同意を得ることまでは変わりありません。同意においては書面などで明確に同意を得ることが求められています。 それ以外にも同意を得る以前に社内で利用目的の変更を行う上での承認を書面で個人情報保護管理者(Pマークの責任者)から得ることが必要となってきます。 【終わりに】 会社で持っている個人情報について利用目的を変更できることにビックリされている方もいあるかと思います。 個人情報保護法を作っている国としても個人情報の利活用をして経済を回すことが目的でもあるので、関連性があればうまくその情報を使うことでビジネスの発展に繋げていきたいと考えています。 違法・不当にならないように専門家の意見を聞きながら会社の個人情報を使っていけれるとビジネス活用がうまくいくことにもなります。
-

2020.11.23
添付ファイルはそのまま送ってOK?パスワード付きzipファイル廃止の発表についての見解
先日、中央官庁でパスワード付きzipファイルによるメールでの添付ファイルの送信を廃止する旨の発表がありました。 それに伴い、プライバシーマーク制度を扱っているJIPDECなどもパスワード付きzipファイルでのセキュリティ対策を推奨しないことを発表するなど、情報セキュリティ・個人情報保護の世界にかなりの衝撃が走っています。 無駄を省く意味では画期的な発表でもあります。 そもそも多くの会社で使われているこのセキュリティ対策ですが、下記のような流れになります。 ①添付するファイルを、適当なパスワードを使って暗号化したZIPファイルに変換する。 ②zipファイルをメールに添付して送信する。 ③続いてそのzipファイルのパスワードをメール送信する。 企業のセキュリティ基準にも明記されているものとなるので、「効果あるのかな?」と思いつつも、毎日行っている方も多い人もいるのではないでしょうか。 この画期的な発表により、今後会社でのメールでの情報送信はどのように変わってくるのでしょうか。 添付ファイルはどんなものであっても、そのまま送ってしまって大丈夫??それとも昔に戻って紙やCD-Rなどを郵送する?? 今回はパスワード付きzipファイルの扱いについて、書いてみたいと思います。 【なぜ、パスワード付きzipファイルを廃止するのか】 河野太郎大臣がはじめた「目安箱」のデジタル庁版「デジタル改革アイデアボックス」は、広くデジタル化への意見やアイデアを広く募っているものとして注目を集めています。 「パスワード付きZIPファイルの添付廃止」の廃止のキッカケはこちらでの提案であり、そこから平井デジタル改革担当大臣の発表にいたります。 暗号化した添付ファイルを送って、その直後にパスワードが来るPPAPと言われる日本特有のメールの悪慣習。 セキュリティ上も意味がないと言われているし、管理を煩雑にしている。 行政はPPAPをやめるとともに、PPAPメールは受け取らないとしたらどうか。 ※デジタル改革アイデアボックスPPAP(暗号化zipの添付廃止)から引用 廃止の理由として、下記を挙げています。 zipファイルのパスワードの扱いは、セキュリティレベルを担保するための暗号化ではない 押印廃止と同様に「今までやってきたからみんなやって」ことにすぎない。 スマホでメール内容を確認できないのも致命的 廃止の会見時に「パスワード付きzipファイルに代わる新しい手段については、デジタル改革アイデアボックスで募集したい」とも話をされていました。 それ以外にも下記のような懸念事項が考えられます。 誤送信の対策として意味がない ※最近はパスワードが自動送付されるツールも多く意味をなさない セキュリティの対策として意味がない ※パスワード自体は10桁程度であればフリーソフトによる総当りで開いてしまうため クライアントへマルウェア付きの添付ファイルを送ってしまった場合、暗号化されるためスキャンができず素通りしてしまう ※最近流行っているemotetで悪用されており、後続のicedIDでも添付ファイル暗号化が確認されている ではこれらについて解説を加えて行きたいと思います。 情報セキュリティ上、意味のない作業 添付ファイルを暗号化すること自体は情報セキュリティ上有効なものではあります。 1つ付け加えると暗号化を解除するパスワードはメール以外の方法で相手に渡すことが出来てようやく担保されることです。 ですが、「同じメールで続けてパスワードを送る」ことは、「メールは盗聴される可能性があるので危ない」ので、実は何の意味もないこと作業になっているのです。 企業における情報セキュリティ・個人情報保護の意識の向上により、メール暗号化の一種であるS/MIMEの方式などはなかなか手間もかかり大変なものでもありました。 そんななか、多くの企業で採用されたのが、「誤送信対策上有効である」と推奨されてきた「パスワード付きZIPファイル」になります。 これはプライバシーマークの審査機関でも推奨されるリスク対応策として認知され、プライバシーマークを取得している企業の多くで実施され、実施されていない場合は指摘されたりもしていました。 JIPDECの突然の発表 プライバシーマークの認証機関でもある一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が「パスワード付きファイルのメール送信は以前から推奨していない」と突然見解を公表しました。 ※一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)からの公表文引用 これは画期的な発表でもありますが、多くの審査においては「パスワード付きZIPファイル」を行うことを審査で指導していた実情もありますし、推奨していないにしても行っているプライバシーマーク取得企業に対して、「推奨していない」旨をこれまで一度も話をしていなかったことは、少し無責任だと考えます。 ※情報サービス産業協会審査基準から引用 実際に一部のプライバシーマーク審査機関では上記の23条に記載の通りで、「個人情報を含む添付ファイルにはパスワードの設定などの措置を講じること」と審査の基準にも記載されています。 JIPDECにはプライバシーマークの認証機関として正しい指導をしてもらいたいところです。 添付ファイルのセキュリティチェックのすり抜け 最近、EMOTETやIcedIDと言ったマルウェア(ウイルス)が世間を賑わせ、猛威を奮っています。 これらのマルウェアは添付ファイルに身を潜め、受信者に添付ファイルを開かせることで感染するのですが、「パスワード付きZIPファイル」で送られてくることも多いのです。 パスワード付きZIPファイルはパスワードがないと開くことが出来ないのは当然のことです。 そのため、ウイルス対策ソフト等によるチェックが効かずマルウェアが仕込まれた添付ファイルを受信していしまうリスクが高まってきます。 欧米などでは「パスワード付きZIPファイル」をブロックしている状況も増えてきています。 日本でもfreeeがパスワード付きファイルのメールを受信拒否を公表しています。 ※freee株式会社によるプレスリリースから引用 業務効率の低下 「パスワード付きZIPファイル」は送信者・受信者ともに作業への負担をかなり多くします。 1か月手作業でパスワード設定やメールを送信する行為をすることで5時間~6時間時間を使ってしまう。という見解もあります。 また、スマートフォンでは「パスワード付きZIPファイル」を開くことにも一苦労するため、現代の仕事の仕方には合っていない可能性も高いと言えます。 これからの電子ファイルの送付方法 では、今後はどのように電子ファイルを送付することになるのでしょうか。 下記のような方法が考えられます。 メール以外の手段でパスワードを伝える 従来通り。パスワードロックはしつつもパスワードは別手段で送付する。これは従来通りの手段である意味一番安全かもしれません。 ショートメッセージ、電話、チャットツールなど、メールとは別の手段でパスワードを伝える形です。 事前に示し合わせていれば、都度変える必要もないかと思います。 ですが、上述した「パスワード付きZIPファイル」を受信拒否する企業に対しては無意味なものです。 別のコミュニケーションツールの利用 最近はチャットワークやslackと言ったチャットツールがメールに代わるコミュニケーションツールとして利用されています。 こういったものでファイルを送付することに完全切り替えることも1つです。 ツール内は暗号化もされており、安全でもあると言えます。 オンラインストレージの利用 box、GoogleDriveと言ったオンラインストレージを使い、ファイルのリンクを送ることも1つの手段になります。 この方法でもやり方はいろいろとあります。 共有ストレージの作成 送り先とファイルを共有するフォルダを作っておき、送付を目的とするファイルのリンクを送る形です。 この方法ですと万が一メールを誤送信してしまったとしても、共有フォルダにアクセスする権限がなければファイルを開くことも出来ないので安心です。 ファイル送付用サービスの作成 もう1つはファイル送付に特化したサービスの利用です。 以前からファイル容量の多いものを送る時に使われていたものを常時利用に転用する形です。 そのまま添付して送る 極論かもしれませんがZIPも何もせずそのまま送る形です。 EMOTETやIcedIDといったマルウェアが流行している現状ですとウイルス対策ソフトなどで検査が行われる添付ファイルの方が安全ある可能性が高いという考えです。 「パスワード付きZIPファイル」を受け取り拒否する会社が増えつつある状況ですと、さほど機密性が高くないファイルはそのまま送ることも安全かつ確実かもしれません。 まとめ 意味があるのか。と悩みながらやってきた「パスワード付きZIPファイル」ですが、今回のデジタル化の流れの中で身近なところが大きく変わった。と思われる方も多いのではないかと思います。 ですが、これまで長年やってきたことにもなるので、いきなり廃止となると戸惑い、不安も多いのではないかと思います。 自分の会社ではどうすべきなのか。など悩まれる方はぜひご相談ください。 関連記事:PPAP形式とは何か
-

2020.11.17
個人情報の開示等の請求って何?もしものための準備をしましょう。
個人情報保護法の中で、会社に対して自身の個人情報を開示や削除を要求する権利があります。 いわゆる、開示等の請求です。 日本では個人情報保護法に則ったこの開示等の請求がなかなかなされていない現状もあり、事例が乏しいところす。 実際に会社としては開示等の請求があった場合にどう対応したら良いのか。が分からないことが非常に多い状況です。 今回はそんな開示等の請求についての流れをお話したいと思います。 【開示等の対象となる個人情報】 まずはどんな情報がこの開示等の対象になるかです。 基本的には下記のようなものが対象例になります。 ・会社の従業員情報 ・直接取引する相手先の情報 ・ECサイト等であれば、サイトの利用者・購入者情報 端的に言い換えると自分(会社)が直接個人情報の本人からもらった情報・それに関連する個人情報が対象になります。 言い換えると委託・受託の関係で委託元から一括でもらった個人情報は開示等の対象外と考えてもらって大丈夫です。 ざっくり定義を話したとしても、いざ本番となるとどこまでが対象か把握出来ないかと思います。あらかじめ、リストを作成するなどして対象となる個人情報にどんなものがあるのか作っておくといざという時に途方に暮れることがないと思います。 【開示等にはどんな種類があるのか】 開示等と一括りにしていますが、実はいろいろと種類があります。 利用目的の通知:どんな目的で自分の個人情報を利用しているのか明確に教えて欲しい 開示:会社が自分の個人情報についてどこまでどんな情報を知っているのか教えて欲しい 訂正、追加、または削除:開示された個人情報に対して内容の訂正、追加、削除を要求する 利用又は提供の拒否:実際に自分の個人情報を使うことを停止してもらう これだけのことが「開示等」の一言の中に含まれています。 これらの内容、関係性をなかなか全て詳細に把握している人もいないかと思いますが、把握出来ていないと、いきなり俺の情報を削除しろ!と言われて削除してしまう。なんてことが起きる可能性があります。 【対応前の準備】 次に準備しなければならないことですが、下記ような準備が必要です。 ・申請、回答書式等の用意 ・窓口、担当者の設置 ・連絡先等の文面作成、公表 まずは書式の準備です。 開示等を請求する時の申請書とその回答を説明する回答書のようなフォーマットが必要になります。 申請書には「請求者の氏名」、「住所等の連絡先」、「本人確認した書類の種類」、「請求内容」、「会社が個人情報の提供を受けた時期や方法」、「代理人が請求するのであればその詳細」などが必要になります。 回答書については、実際に結果を書くことになるので、ある程度フリーフォーマットでも良いでしょう。 次に「窓口・担当者の設置」ですが、責任者・担当者は明確に定めてください。電話に出た人が勝手に対応するなんてことがないようにしなければなりません。 プライバシーマークを取得している会社であればプライバシーマークの責任者が就くことが多いかと思います。それ以外ですと個人情報を一番扱う部門の責任者や担当する役員の方なども例になります。 責任者・担当者を決めたら、必ず社内に周知をしてください。 先ほど触れた通り、電話に出た人の勝手な判断で対応することを防ぐためです。開示等の請求の問い合わせが来たら、担当に電話を回す。が重要です。 個人情報の開示等の請求の際にはクレームになっている可能性も否定が出来ず、不十分な対応やたらいまわしはトラブルの元になります。 3つに目には「連絡先等の文面作成、公表」です。 「開示等の請求の流れ」、「連絡先(電話・メール等)」、「本人確認の手段」などありますが、1つ重要なことは開示等にかかる手数料です。 明確な価格は法律等で決まってはいません。ただ、高額過ぎる金額を提示することは出来ません。ここでの価格設定はある意味開示等の請求を会社がどう対応するかのキモにもなってきます。 こういったことを記載した文面は会社のHPなどで公表することが主流になります。 【最後に】 最後にこの開示等の請求は滅多に発生することはありません。 ただ、手順や内容を把握出来ていないと、もし発生した時に対応が不十分になってしまう可能性があります。 例えば、本人確認をしっかりせず個人情報を開示したことで個人情報が第三者に漏えいしてしまった。なんてこともあり得ます。 なかなか浸透していない制度にもなりますが、ここをしっかり対応することで個人情報が適切に管理出来ている会社であることをPRすること可能になります!
-
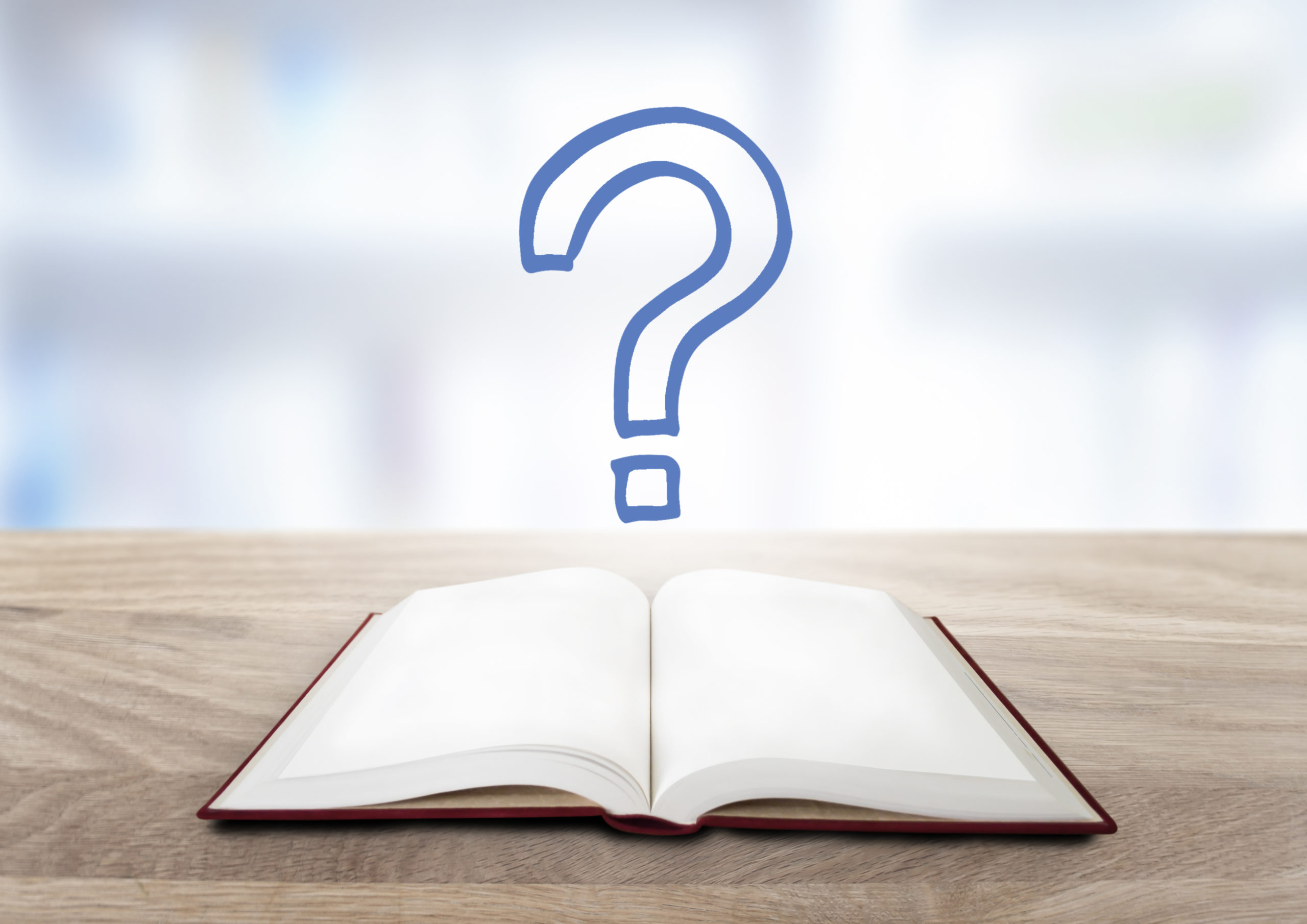
2020.11.14
コンサル任せにすべき?審査機関はどうすべきか。
Pマークの取得にあたって、審査機関は切れない存在です。 しかも、審査機関は約20機関もあるので、違いも何も分からない人が多いのではないでしょうか。 コンサルに支援を依頼している方はおそらくコンサルの言う通りに審査機関を選んでしまっているのではないかと思います。 審査機関については、別のブログで詳細を紹介していますのでそちらを読んで頂きたいですが、もう少し審査機関を選ぶにあたって踏み込んだ内容をお話します。 【コンサルに任せるメリット】 初めてPマークを取得する際にコンサルを入れている会社は多いです。 審査機関についてもコンサルから説明があるかとも思います。 多数の実績があるコンサルであれば、経験や噂からあの審査機関が良い、あそこも審査機関はダメ。という話を少なからず分かっている状況です。 そのコンサルからこの審査機関にしましょう!と言われると恐らくそのまま決まることが多いと思います。 だいたいのメリット内容としては ・指摘が少ない ・審査ラク ・多少のミスは許容してくれる と言った形でPマークの取得を目指す会社にとっては非常にメリットがある内容を説明されます。 端的に言い直すと「楽して審査が通過できます!」と言った内容ですね。 【コンサル任せにするデメリット】 逆にコンサル任せにするデメリットはあるのでしょうか。 メリットの話だけだと皆さんにとっては楽してPマークが取れる可能性が高まるのでデメリットがないように感じます。 ですが、デメリットもあります。 その1つはお金の部分です。 コンサルが勧める審査機関は会員企業向けにPマークの審査を提供する審査機関です。 以前のブログで紹介した「判断基準の②」に該当する審査機関ですね。 デメリットを箇条書きにすると下記のような形です。 ・その審査機関である団体に入会する(入会金発生する) ・年会費が発生する(ランニングコストとして毎年発生) ・審査機関は東京にあるので東京・関東近郊以外の会社にとっては交通費が数万円~10万円強かかる可能性がある(審査員は2名来ますし、宿泊を伴う場合は宿泊費もPマーク取得を目指す会社側の負担です) と言った形です。 【最終的にどうすべきか】 審査がラクという意味はコンサルが楽できる。という意味につながります。 Pマークの現地審査にコンサルが立ち会えませんので、現地審査での対応などは皆さんの負担になりますが、、、全体的な取り組みにおける文書作成や修正はコンサルの負担になるはずです。 そこには取得する会社である皆さんが多額の金銭的な負担がかかることを考慮されているかはなんとも判断がつかない状態です。 ですので、特定の審査機関を強要するコンサルではなく、選択肢の1つとして提供し、どの審査機関でも対応可能なコンサルタントにPマーク取得の支援を依頼することが、取得を目指す皆さんにとってベストパートナーとなると考えます。
-

2020.11.13
審査機関ってなに?Pマークの審査機関について
Pまークを取得するためには審査機関からの審査を受けてからではいと取得することが出来ません。 初めてPマークを取得する方からすると審査機関ってなに?どこにあるの?何してくれるの?など?なことだらけだと思います。 今回はそんなPマークで絶対関わってくる審査機関についてご紹介します。 【審査機関とは】 まず、Pマーク審査機関は何かですが、その名の通りPマーク取得・更新のための審査をしてくれるところです。 2020年11月時点で20の審査機関が存在します。 下のリストは19機関しか載っていないですが、Pマーク制度の一番大元となるJIPDECは認証機関兼審査機関でもあるので、載っていません。 すべての審査機関がJIPDECから委託を受けて審査を行っています。 その上で、どこに提出すべきかは皆さんの会社がどこにあるのか。どういった業種なのか。ご自身の会社が加入する団体が審査機関になっていないか。が判断基準になります。 【判断基準その①-業種-】 まず、業種として絶対に拘束される業種があります。 それは医療関係の機関や会社です。具体的には病院やレセプト管理と言った医療関係の個人情報を扱うところです。 こう言ったところは絶対に一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)に申請しなければなりません。 理由としては、医療系のPマークは他とは違い特別な基準があり、より専門性が必要とされるからです。 クリアスでは医療系のPマークの支援実績もありますので対応可能です。 【判断基準その②-会社が加入する団体-】 ①に該当しない場合ですが、皆さんの会社が加入している団体が審査機関となっている場合、そちらに申請することも可能です。 主にはIT関係の団体が多いですが、印刷関係の団体もあり、専門性を理解してもらった上で審査を受けることができるメリットの1つです。 デメリットとしては、東京から審査員が向かうことになるため、東京・関東近郊以外の会社にとっては交通費が高くなってしまうことが上げられます。 Pマークの取得をキッカケに加入することが可能な団体もありますが、入会金・年会費がかかるところが多いため、割高になってしまいます。 【判断基準その③-地域-】 ①に該当せず、②の団体に申請しない場合は各地域を担当する審査機関に申請することになります。 北海道、東北、関東、中部・東海・北陸、関西、中四国、九州・沖縄とそれぞれ地域を担当する審査機関があるのでそこに申請をします。 メリットとしてはご自身の会社がある地域の審査機関に出すため、交通費が②に比べると安く済むケースがほとんどです。 審査料金も安くはないので、ここで費用を抑えることは1つ重要なポイントであると言えます。 デメリットとしては、審査機関によっては評判が悪いところもあるので、選べない以上それを受け入れることが必要となります。 いろいろと迷うなら地域を担当する審査機関に申請することは無難とは言えます。 このように審査機関は多数あり、ぶっちゃけどこにすべき?と悩む方も多いと思います。 支援するコンサルタントに相談することも1つだと言えます。 ただ、コンサルタントが楽するためだけの理由で審査機関を選ぶことはお勧めしません。 その詳細はこちらのブログも参照してみてください。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能