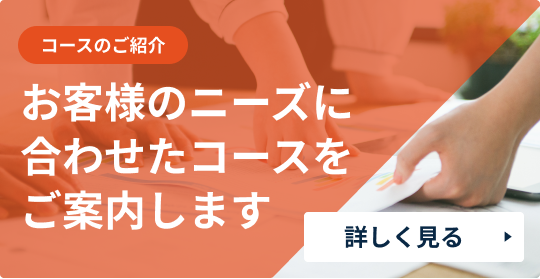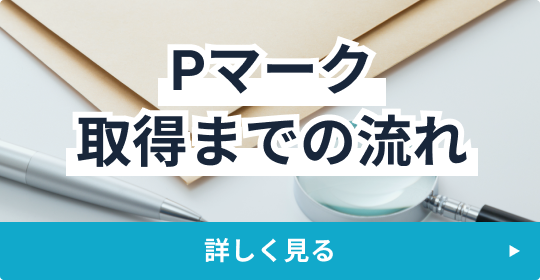INFORMATION
お役立ち情報
-
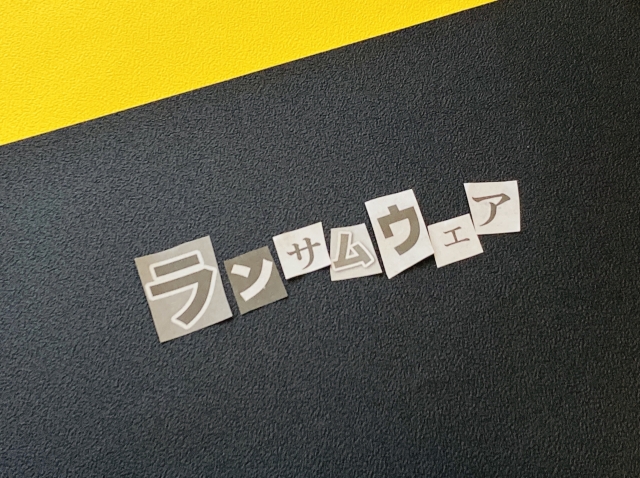
2025.10.15
アサヒグループHD ランサムウェア被害」から学ぶ、プライバシーマーク企業が取るべき個人情報保護の実践対策
1. 導入:プライバシーマーク認定企業にとってのリスク プライバシーマーク(Pマーク)は、「個人情報を適切に取り扱う体制を備えていること」を認定する制度であり、企業に対して個人情報保護への一定の信頼性を与える制度です。 しかし、サイバー攻撃やランサムウェア被害は、単なる「機密情報流出」だけでなく、個人情報漏えいにつながる可能性が高く、Pマーク企業にとっては認定維持リスク、社会的信用失墜リスクが非常に高い脅威です。 本記事では、アサヒグループHD の被害事案を題材に、「プライバシーマーク取得・運用企業」が特に注視すべきポイントと対策について解説します。 2. アサヒグループHD の被害概要と流出可能性 報道・公表内容を整理すると、以下のような被害・可能性が確認されています。 ⚠️ 2025年9月29日、システム障害を公表。後にランサムウェア攻撃によるものであると発表。 ⚠️ 攻撃により、サーバーが暗号化された可能性。 ⚠️ 個人情報の流出可能性を認め、公表。 ⚠️ 受注・出荷業務停止、メール受信停止、基幹システム停止といった業務影響を伴う障害。 ⚠️ ダークウェブ上で「アサヒHD のデータを盗んだ」とする主張(Qilin による二重脅迫的手法報道)も複数報道。 このように、被害が単なるシステム障害にとどまらず、個人情報の流出リスクを伴っている点が、プライバシーマーク運用者にとって重大な関心点になります。 3. プライバシーマーク視点で見る、この事案での課題と原因 以下は、プライバシーマークの観点で、今回の事案から浮かび上がる課題と原因仮説です。 3‑1 個人情報識別と保護範囲の甘さ Pマーク運用では、まず「どのデータが個人情報か」を明確に識別し、保護対象とする範囲を定めなければなりません。 しかし、ランサムウェア被害では、機密・業務データに混在して保存されている個人情報も一括で暗号化・流出されるケースがあります。 もし個人情報識別が不十分で、保護対象外と誤認されたデータがあったなら、漏えい対象として扱われず、しかも対策が甘くなる恐れがあります。 3‑2 データ最小化・アクセス制御不備 Pマークでは「収集最小化」「不要データの削除」「目的外利用禁止」が重要原則です。 しかし、実務面で個人情報を広範囲に保存しすぎると、被害時のリスクが拡大します。 また、アクセス権限設定が甘いと、ランサムウェア侵入後に横展開して多数の端末・システムに到達してしまいます。 3‑3 保存データ・ログ管理の不徹底 Pマークの運用要件には、ログ取得・アクセス履歴管理・異常検知が含まれます。 被害企業の中には、ログが十分に取得されていなかった、またはログ内容・保存期間が不足しており、感染源特定・流出範囲把握が難航するケースがあります。 今回のアサヒ社事案でも、流出可能性が後から認められたことから、初動段階での把握やログ分析が追いつかなかった可能性があります。 3‑4 外部送信・データ持ち出し対策の不備 プライバシーマーク運用上、外部への個人情報送信時の暗号化、持ち出し管理、外部委託先管理が必須です。 ランサムウェア攻撃において、攻撃者は「暗号化」だけでなく「データ外部転送(盗取)」を行うことが多く、二重脅迫手段を用います。 外部送信対策が十分でないと、外部に持ち出されてしまい、漏えい事故となります。 実際、この事案では「流出可能性」という表現が複数報道されており、外部送信の痕跡を調査中である旨も公表されています。 これらの課題を前提に、プライバシーマーク取得企業が取るべき対応策を次に示します。 4. Pマーク企業が取るべき個人情報保護強化策(対策) 以下は、プライバシーマーク運用の枠組み・認定要件の観点を踏まえた、実践的な強化対策案です。 4‑1 個人情報の分類と取扱範囲設計 ✅ どの情報が「個人情報」「要配慮個人情報」かを明確に定義・分類 ✅ 業務部門における個人情報取扱マトリクスを整備(どこで扱う、誰が扱う、どこへ送信するか) ✅ 不要になった個人情報は、速やかに安全に廃棄・削除 4‑2 アクセス制御と最小権限原則の徹底 ✅ 個人情報取扱システムへのアクセスは「必要最小限の権限」に限定 ✅ 部門・職責に応じたアクセスロール設計と定期的な見直し ✅ アクセス権変更・削除プロセスを明確化・運用 4‑3 暗号化・マスキング・匿名化の活用 ✅ 保存データ(at rest)や転送データ(in transit)に対する暗号化を適用 ✅ 個人情報表示箇所でのマスキング(氏名イニシャル化等)、必要に応じて匿名化処理 ✅ データベースやログにも暗号化をかける、キー管理運用を整備 4‑4 ログ管理・追跡性確保・異常検知強化 ✅ 個人情報アクセス・編集・出力操作のログを詳細に取得 ✅ ログ保存期間・整合性担保(改ざん防止措置)を確保 ✅ ログ分析ツール・異常検知ルールを導入し、アラート体制を整備 4‑5 データ出力・持ち出し・外部連携制御 ✅ 個人情報を含むファイルの出力制限(USB不可、クラウド転送制限など) ✅ ファイル転送・持ち出し時の承認プロセスと暗号化必須ルール ✅ 外部委託先への個人情報提供に際して契約条件・安全管理措置の明示 ✅ API 連携やクラウドアクセス時にも暗号化通信と認証制御 4‑6 定期的なリスク評価・審査対応準備 ✅ 年次または四半期ごとの個人情報リスクアセスメント実施 ✅ プライバシーマーク審査を想定した評価点・改善ログ整備 ✅ 内部監査・第三者監査を通じてギャップを洗い出し改善 4‑7 利用者通知・漏えい時対応手順明文化 ✅ 個人情報漏えい時の通知義務・対応フローをあらかじめ定めておく ✅ 被害範囲把握、影響者通知、再発防止策提示、報道対応(広報)体制整備 ✅ 漏えいインシデント後の社内手順演習(模擬訓練) 5. まとめとプライバシーマーク企業へのメッセージ アサヒグループHD のランサムウェア被害事例から、企業が注意すべき点は、 単なる「システム障害」ではなく個人情報保護という観点での被害拡大リスクです。 プライバシーマーク認定企業においては、個人情報にまつわる管理体制を強化しておくことが、認定維持のみならず、信頼性・ブランド保護にも直結します。 本記事で紹介した分類・アクセス制御・ログ管理・出力制限・漏えい対応といった対策を、日常運用レベルで確実に実装し、定期的に評価・改善を回すことが重要です。
-

2025.10.14
「個人の識別」と「特定の個人の識別」の違いとは?わかりやすく具体例で解説
はじめに:よくある混同「個人の識別」と「特定の個人の識別」 個人情報保護やセキュリティに関する話題でよく登場する「個人の識別」と「特定の個人の識別」という言葉。 似ているようで意味が異なり、正しく理解していないと法的リスクや誤解を招く可能性もあります。 この記事では、それぞれの意味と違いを具体例を交えてわかりやすく解説します。 「個人の識別」とは? 定義:ある情報により、ある個人が他の個人と区別できること。 これは、誰かを「他の人と違う人だ」と認識できる状態を指します。 ただし、その情報だけで誰なのか(氏名など)まではわからないこともあります。 具体例: あるウェブサイトの訪問者ID(例:User1234) 音声認識による「この声は過去にも聞いた声」と認識すること アバターや仮名で投稿しているSNSアカウント これらは「同じ人が繰り返し現れている」とわかるが、「誰か」はわからない状態です。 「特定の個人の識別」とは? 定義:ある情報により、その人が誰なのか(氏名・住所など)までわかる状態。 つまり、実在の個人を特定できる情報が含まれている、あるいは組み合わせによって判明してしまう場合です。 具体例: 氏名+住所 マイナンバー 顔写真(AIが本人特定できる精度なら)特定の社員番号と社内データベースの紐付け これらは、単体または他の情報と組み合わせて、「この人だ」と特定できるものです。 まとめ:違いをシンプルに理解するコツ 種類 意味 例 特定の個人が誰か判明するか? 個人の識別 区別はできるが、誰かは不明 ユーザーID、仮名SNS ✕ 特定の個人の識別 誰なのかが明確 氏名+住所、顔写真 ○ ポイントは、「識別」は区別、「特定の識別」は本人を判定できるという違いです。 企業・個人が注意すべき点 近年では、個人情報保護法の観点から「識別できる」情報も慎重に扱う必要があります。 🔷 クッキー(Cookie)などのウェブトラッキング情報 🔷 位置情報や端末情報 🔷 SNSの投稿履歴 一見匿名でも、複数の情報を組み合わせることで個人が特定できる場合があります。 これを「識別可能性」と言い、企業が取得する際は利用目的の明示や同意取得が必要になります。 おわりに:正確な理解がトラブル回避の第一歩 「個人の識別」と「特定の個人の識別」の違いを正しく理解することは、情報セキュリティやプライバシー保護の基礎になります。 特にビジネスやIT分野に関わる方は、曖昧にせず明確に把握しておくべきです。
-
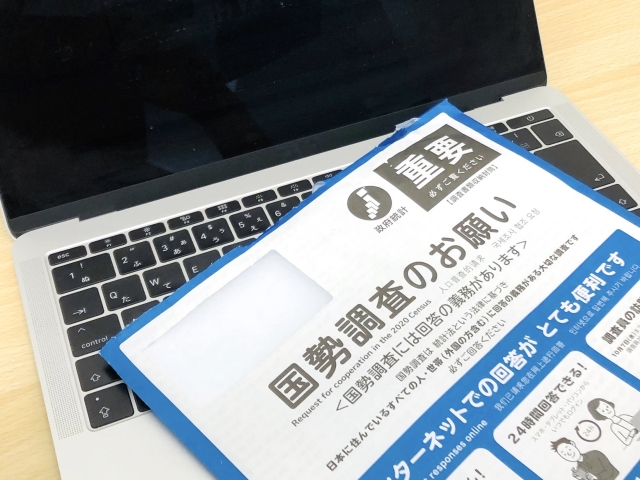
2025.09.26
【国勢調査と個人情報】情報漏洩リスクや対策を徹底解説
国勢調査とは?個人情報との関係性 国勢調査(こくせいちょうさ)は、日本に住むすべての人を対象に5年ごとに実施される政府主導の統計調査です。 国勢調査では、「氏名」「性別」「年齢」「職業」「住居の種類」など、非常に詳細な個人情報が収集されます。 このため、「国勢調査で個人情報は本当に守られているのか?」という疑問を持つ人が増えており、プライバシー保護の観点からも注目されています。 国勢調査における個人情報の問題点 1. 調査員による個人情報漏洩のリスク 国勢調査は、調査員が紙の調査票を配布・回収する形式が今も一部で採用されています。 以下のような人的ミスによって、個人情報が漏洩する事例があります。 他人の調査票を誤って渡す 回収した調査票を紛失 身分証明書を提示せず訪問 これらは国勢調査における個人情報保護の重大な課題です。 2. インターネット回答とサイバーセキュリティ 最近はオンライン回答が主流になりつつありますが、「調査ID」や「パスワード」が記載された通知書が盗まれたり、**偽サイト(フィッシング詐欺)**が出現するなど、新たなセキュリティリスクも浮上しています。 3. プライバシーへの不安と拒否感 国勢調査で収集される個人情報の詳細さに対して、「なぜここまで聞くのか?」「悪用されるのでは?」といった不安の声も根強くあります。 一人暮らしの女性の不安 高齢者のセキュリティ知識の不足 調査員への不信感 こうした不安要素は、回答率の低下にもつながります。 国勢調査における個人情報漏洩の事故事例 【事例1】2010年 愛知県で調査票の紛失事故 調査員が回収した調査票を紛失し、職業・家族構成などの個人情報が第三者に流出する恐れがあるとして問題となりました。 【事例2】2020年 偽サイトによるフィッシング詐欺 国勢調査公式サイトを模した偽サイトが出現し、ログイン情報や個人情報を不正に取得する事案が発生。総務省は注意喚起を行いました。 【事例3】調査票の誤配・開封事故 誤った住所に調査票が送付され、別人が開封してしまったケースも報告されています。 【対策まとめ】国勢調査と個人情報を守るために必要なこと 今後は「紙の調査票の完全廃止」「本人認証付きオンライン回答の義務化」なども検討されるべきでしょう。 まとめ:国勢調査と個人情報保護は両立できるか? 国勢調査は、社会の未来を支えるための大切な統計データを得る手段ですが、個人情報の扱い方次第では信頼を失うリスクもあります。 信頼性を高めるには、以下の3つがカギです。 🔶 情報管理体制の見直し 🔶 技術的なセキュリティ強化 🔶 国民への説明責任と透明性 個人情報を守りつつ、国勢調査に協力できる体制づくりが急務です。
-

2025.09.09
2024年度 Pマーク付与事業者における「個人情報取扱い事故調査」から見る、コンサル視点の課題と対策
2025年9月8日、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が「2024年度 個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」を公表しました。 Pマーク付与事業者1,866社からの報告による事故件数は9,322件にのぼり、前年度に比べ報告事業者数は86社減少、事故件数は114件増加という結果となりました。 注目すべき統計内容 ●「PMK500第12条第3項」に該当、つまり要配慮個人情報や財産的損害の可能性がある事故は、3,120件にもおよびました。 ●事故の発生事象別では、「漏えい」が6,130件(75.8%)と圧倒的に多く、続いて「紛失」が727件(9.0%)。 ●事象分類別では「誤配達・誤交付」が最多(3,172件/41.4%)、次いで「誤送信」(2,250件/29.4%)、「紛失・滅失・毀損」(866件/11.3%)、「誤登録」(425件/5.6%)、「不正アクセス」(346件/4.5%)という順です。 ●原因別では、「作業・操作ミス」が最多(4,324件)、続いて「手順・ルール違反作業、操作」(3,633件)、「確認不足」(3,280件)と、人為的なミスが事故の根幹を占めています。 ●媒体別では、「紙」が48.8%、「電子データ」が40.7%。まさにアナログとデジタル双方での取扱いがハザードであることを示しています。 ●流出情報の種類は、「氏名」(6,820件)が最多、続いて「住所」(2,628件)、「電話番号」(1,689件)、「メールアドレス」(1,529件)。さらに「クレジットカード情報」は743件、「マイナンバー」は44件と少数ながらセンシティブ情報の漏えいも確認されました。 コンサルタントとして見える「気づき」と示唆 1. 人為的ミスへの対策がもっとも喫緊の課題 統計から明らかなように、事故原因の大部分は「作業ミス」「ルール違反」「確認不足」といった人為的な要因です。これはすなわち、手順の明確化・教育の徹底・チェック体制の強化が最も有効かつ喫緊の対策であるということを如実に示しています。 2. アナログ対応でも気を抜かない、媒体横断的な対策が必要 意外に多かった「紙媒体」での事故(48.8%)。これは、印刷文書や外部持出し時のリスク管理がまだ整備されていない現状を反映しています。紙でも電子でも、同等にリスク評価し、物理管理や廃棄ルールなども明文化・運用すべきです。 3. センシティブ情報流出の影響に備えるべき 「クレジットカード情報」「マイナンバー」といった高度な個人情報の漏えいは件数こそ少ないものの、発生した際の影響は甚大です。特にこれらの情報を取り扱う事業者には、二段階認証・アクセス制御・暗号化・インシデント対応体制の整備が求められます。 4. 事故が発生した際の「事後対応力」も重要 単なるリスク削減策だけでなく、「丁寧な事後対応」も評価ポイントです。事故発生後の顧客・関係者への説明、再発防止策の迅速な実施、影響の最小化に向けた対応を組織文化として定着させることが、信頼回復につながります。 Pマークコンサルティング会社として「提供すべき支援内容」 A. ドキュメント整備と手順の明文化 業務フローの可視化とチェックポイントの導入(例:「誤送信防止チェックリスト」など)。 紙媒体対応ルール(例:机上の書類管理・持ち出し時の許可プロセス・シュレッダー処理手順)と電子データ管理ルール(暗号化・アクセス権限・送信時ワーニング機能など)の整備。 B. 全社教育と定着化支援 定期的な全従業員向けセミナーやeラーニングにより、ミスが起きやすい事象を共有。 内部監査制度構築による、実行状況のモニタリングと日常的な改善の仕組み化。 C. インシデント対応体制の強化支援 インシデント発生時の対応計画書(テンプレート)の提供。 模擬演習(事例ベースの再現訓練)を通じたリハーサルによる迅速対応力の向上。 D. 定常運用・更新支援の提供 Pマーク取得後も更新審査を見据えた継続的支援(文書管理、内部監査サポート、審査対応支援など)。 前掲のようなケースでは、単年度のみならず継続支援可能なプラン(例:文書スリム化・教育支援・運用相談など)が信頼構築に寄与します。 結びに:組織の文化として「個人情報保護」を根付かせる 今回の報告は、あらためて「人間のミス」が最も大きなリスク要因であることを浮き彫りにしました。Pマークは単なる形だけの認証ではなく、「組織文化としての個人情報保護」を構築し、その一部として事故防止・再発防止の取り組みが継続的に行われているかどうかを示すものです。 私たちコンサルティング会社は、単なる書類整備代行ではなく、**現場の運用に“寄り添う支援”**を通じて、企業が自らの力で継続的に安全を担保できる体制を構築していきたいと考えています。 今回の統計から見える課題を、自社のリスク管理の足がかりとし、より強靭な情報管理体制の構築に繋げていきましょう。
-

2025.05.17
【2025年最新】Pマーク更新支援のポイントと対策まとめ
企業が信頼を築く上で欠かせない「プライバシーマーク(Pマーク)」制度。 特にPマークの更新は、取得時以上に重要なプロセスです。 しかし、更新作業は手間も多く、制度の変更や審査基準の見直しに追いつくのは大変です。 この記事では、Pマークの更新支援に関する具体的なポイントや、更新に必要な準備について詳しく解説します。 Pマークの維持にお悩みの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。 (※詳しい支援サービスはこちらのサイトをご覧ください) Pマーク更新とは?基礎知識をおさらい プライバシーマークの有効期限は2年間。この期間が過ぎる前に「更新申請」を行い、再審査を受ける必要があります。 更新審査では、初回取得時と同じく個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の運用状況がチェックされます。 Pマーク更新でよくある課題 法改正への対応漏れ 個人情報保護法の改正が頻繁に行われており、PMS文書の見直しが追いついていない企業も多いです。 教育記録や監査記録の不備 更新では、過去2年間の教育実施記録や内部監査記録など、実績ベースの運用が重視されます。 担当者の引き継ぎ不足 担当者の交代によってノウハウが継承されず、更新作業が滞ることも。 Pマーク更新をスムーズに進めるための支援ポイント ✅ 文書類の事前チェック 変更が必要な文書をリストアップし、最新版に更新しましょう。 特に「個人情報取扱規程」や「安全管理措置」に関する文書は要確認です。 ✅ 教育・監査のスケジュール管理 年1回の教育と監査は必須です。忘れがちな記録の保管・整備も忘れずに。 ✅ 外部の専門家によるレビュー Pマーク更新支援サービスを利用することで、漏れのない対応が可能になります。 特に審査傾向に精通したコンサルタントの活用がおすすめです。 Pマーク更新支援サービスを利用するメリット 🔷 最新の法改正や審査基準に即したアドバイス 🔷 書類作成の負担軽減 🔷 審査対応のリハーサルや模擬指摘対策の提供 まとめ:Pマーク更新はプロの力を借りて確実に Pマーク更新は「毎年の繰り返し」ではなく、常に変化する個人情報保護の最新動向に適応するプロセスです。 自社内だけで対応するのが難しい場合は、外部支援サービスを検討するのもひとつの手です。 更新対応を迷われている方は、こちらのサイトからお気軽にご相談ください。 専門家によるスムーズな支援で、御社のPマーク更新を成功に導きます。
-

2025.05.12
録音ボタンを押す勇気 〜パワハラと個人情報のはざまで〜
「……この録音、本当に大丈夫だろうか?」 ある日、会社員の高橋優子は、自席でスマートフォンの録音アプリに指をかけていた。 理由はただ一つ。職場で日常的に受けるパワハラの証拠を残すためだ。 朝の会議でも、課長の西山から「お前は本当に社会人か?」と怒鳴られ、心が折れそうになる日々。 誰かに相談しても「証拠はあるのか」と言われるだけ。だから、優子は録音という選択肢に辿り着いた。 パワハラの録音は違法?個人情報保護法との関係 ここで気になるのが、「録音は違法なのか?」「相手の許可なしで録るのは問題ないのか?」という疑問です。 特に個人情報保護法との関係が気になりますよね。 ▼ 結論:パワハラの証拠目的の録音は原則合法 日本の法律では、自分が当事者である会話を録音すること自体は違法ではありません。 また、パワハラなどの不法行為に対して証拠を収集する目的がある場合は、「正当な理由」として認められるのが一般的です。 また、録音に含まれる音声は「個人情報」に該当する可能性がありますが、自己の権利保護が目的であれば個人情報保護法の違反にはあたりません。 録音する際に絶対に守るべき注意点 パワハラの録音を行う際は、以下のポイントに注意しましょう。 1. 録音の目的は「証拠保存」に限定する 私的な報復やSNS拡散などの目的で録音を使用すると、名誉毀損に該当する可能性があります。 2. 無断編集はNG 都合よくカット編集した録音は、裁判などで証拠能力が否定される場合もあります。 3. 公開範囲を最小限に 録音データの使用は、社内の人事部や弁護士などに限定しましょう。第三者への無断提供や公開は避けるべきです。 実録:録音でパワハラから抜け出した女性の物語 優子は、パワハラの録音を数週間にわたって続けました。 ある日、満を持して録音データを持参し、再度人事部に相談しました。 録音には、明確な暴言と叱責が収められており、会社も重く受け止めざるを得ませんでした。 結果、西山課長は別部署に異動となり、優子は新しい職場で穏やかな日々を取り戻します。 録音は「自分を守るための正当な手段」 パワハラの被害を受けている方にとって、録音は「最後の砦」となることがあります。 もちろん、法的知識やモラルを守る必要はありますが、泣き寝入りせず、自分を守る手段として録音は有効です。 まとめ:パワハラ対策には「記録」と「勇気」が鍵 🔶パワハラの録音は原則合法。 🔶個人情報保護法違反にはなりにくい。 🔶証拠として録音を活用するには、目的と方法を明確にすることが大切。 もしあなたが今、職場で同じように苦しんでいるなら、まずは状況を記録することから始めてください。 声を上げる準備をしておきましょう。 他にも「パワハラ対策」や「証拠の残し方」に関する記事は、こちらのサイトでも多数掲載しています。 ご参考になれば幸いです。
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能