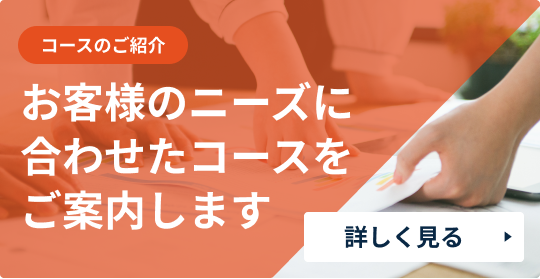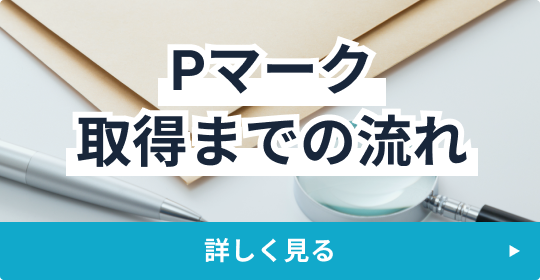INFORMATION
お役立ち情報
-

2025.05.04
退職前に勤怠データを持ち出して労基署へ提出するのは違法?情報漏えいに該当するかを徹底解説!
ある日、佐藤さんから届いた相談。 「吉村さん……ちょっと相談があるんです。会社を辞める前に、自分の勤怠データをUSBにコピーしておいたんです。退職後、未払い残業代の件で労働基準監督署に相談したんですけど……これって、情報漏えいになるんでしょうか?」 そう語るのは、関西のとあるIT企業に勤めていた佐藤健一さん(仮名・30代前半)。 数年間勤めていた会社では、日常的に月80時間を超える残業が当たり前。 それなのに、残業代は「みなし残業」で処理され、申請すらできない空気がありました。 そんな状況に耐えかね、彼は退職を決意。 会社のシステムから自分の勤怠データを抜き取り、退職後、証拠として労基署に提出しました。 ところが、後日…… 前職の人事担当から「社内情報を持ち出すなんて、情報漏えいじゃないのか」と責められ、不安になったというのです。 果たして、佐藤さんの行動は法的に問題だったのでしょうか? 勤怠データって、そもそも誰のもの? まず最初に考えるべきなのは、「勤怠データとは誰のものか?」という問題です。 企業がシステム上で管理しているとはいえ、その中には個人名、勤務時間、休暇取得など、その人の働き方やライフスタイルが詳細に記録されています。 実際、勤怠データには「個人情報」が含まれているため、個人情報保護法の適用対象になります。 しかし、そのデータの「主体」は本人であり、本人には自分の個人情報を開示請求する権利(個人情報保護法 第33条)があります。 つまり、佐藤さんが取得したのが「自分自身の勤怠データ」であり、そこに他人の情報が含まれていなかったのであれば、それだけで違法行為になるとは考えにくいのです。 問題となるのは「どうやって」「何を」「どこに」持ち出したか ただし、すべてが正当化されるわけではありません。 佐藤さんが行ったように、自分の勤怠データだけをUSBに保存して持ち出すという行為が、企業のセキュリティポリシーに違反していた場合、それは**「社内規定違反」**になる可能性があります。 企業によっては「社外への情報持ち出し禁止」や「外部記録媒体への保存禁止」といった規則が定められており、それを破れば懲戒処分の対象になることも。 ただ、佐藤さんの場合はすでに退職済み。企業が後から懲戒処分を下すことは難しく、仮に損害が発生していなければ、損害賠償請求なども現実的には考えにくいです。 一方で、もし佐藤さんが他の社員の勤怠データも一緒に持ち出していた場合、それは完全にアウトです。他人の個人情報を本人の同意なく第三者に提供する行為は、個人情報保護法違反となり、重大な法的リスクを抱えることになります。 「労基署に提出する」は違法ではなく、むしろ守られている行為 ここで重要なのは、佐藤さんが勤怠データを持ち出した目的です。もし彼が、そのデータを使って元職場を誹謗中傷するためにSNS等に晒したのであれば、たとえ自分のデータであっても名誉毀損や信用棄損に問われかねません。 しかし、今回は労基署という公的機関に提出し、未払い残業代の申告という公益性のある目的のために使用しています。 このような場合、「公益通報者保護法」という法律が関係してきます。この法律は、労働者が企業の違法行為を内部告発・外部通報する際、その通報によって不利益を被らないよう保護する制度です。 労基署はその「通報先」として正式に認められており、通報の内容が真実と信じるに足るものであれば、通報者の行為は法的に保護されます。 つまり、佐藤さんのように「自身の労働環境の是正のために」「自身の情報を証拠として」使う行為は、情報漏えいには該当せず、適法とされる可能性が極めて高いのです。 企業側のリスクと対策 一方で、企業側としても、従業員が退職時に情報を持ち出すことは、経営上のリスクとなりえます。 たとえ合法であっても、対応を間違えると「隠ぺい体質」として社会的信用を損ねる恐れもあります。 そのため、企業が講じるべき対策としては以下のようなものが考えられます。 🔷勤怠システムへのアクセス制御(ダウンロード・印刷権限の制限) 🔷社内の持ち出しルールの整備と明文化 🔷従業員への定期的な情報管理教育の実施 🔷内部通報制度の整備と、相談窓口の見える化 加えて、未払い残業や労働環境への不満がそもそも存在しないよう、適切な労務管理と風通しの良い社内文化の構築が、最も根本的な対策となるでしょう。 まとめ:情報漏えいか正当な通報か、それを分けるのは「目的と方法」 佐藤さんのケースは、「情報漏えい」と「正当な権利行使」のはざまにある行為でしたが、法的に見れば、個人情報保護法・公益通報者保護法いずれの観点からも、明確に違法とは言えないものです。 しかし、その正当性を守るためには、「自分のデータに限る」「正規の手段で取得する」「公的機関への提出に限る」など、目的と方法の正しさが不可欠です。 一方、企業側もこのような事例に対して過剰に反応するのではなく、内部に問題がなかったかを冷静に見直し、再発防止と改善に努めることが、長期的には会社の信頼を守る道となるはずです。
-

2025.04.07
難しい個人情報関連用語を小さい子にも分かるように解説!
『個人情報保護に関する用語は、難し過ぎて意味が分からない。』とよくご質問をいただきます。 今回は難解用語トップ3とも言える「匿名加工情報」、「仮名加工情報」、「個人関連情報」について小さい子も分かるよう解説していきます。 ここから記事のしゃべり方が変わりますのでご注意ください(笑) 今からようちえんのおともだちにもわかるように、 やさしいことばで「仮名加工情報」「匿名加工情報」「個人関連情報」のおはなしをするね。 こんにちは!たろうくんのおはなし たろうくんは、ようちえんにかよっている5さいのおとこのこ。 すべりだいやブロックあそびがだーいすき♥ せんせいは、「みんながどんなあそびをしているか、すこしだけしらべてみたいな」って思いました。 でも、そのときにとっても大事なことがあるの! それはね、**「みんなのひみつはちゃんとまもること!」**なんだよ。 1.仮名加工情報(かめいかこうじょうほう)ってなに? たろうくんのほんとうのなまえを「★くん」にかえたり、 「にじいろ町5-6」っていうじゅうしょを「にじいろ町」だけにしたり…。 こんなふうに、「ほんとうのじょうほう」をちょっとだけかえて、だれかわからないようにしたものを 「仮名加工情報(かめいかこうじょうほう)」っていうんだよ。 でもね、すごーくがんばったら、「★くんって、たろうくんじゃない?」ってばれちゃうこともあるから、 **まだまだ注意がひつよう!**なの。 2.匿名加工情報(とくめいかこうじょうほう)ってなに? こんどは、ぜーったいにだれかわからないようにしちゃおう! たとえば… 「5さいの子が10人、すべりだいであそんでいました」 「ようちえんで一番にんきなおもちゃは、レゴでした!」 こんなふうに、ひとりひとりのなまえもないし、だれのことかわからないようにしたじょうほうを 「匿名加工情報(とくめいかこうじょうほう)」っていうよ! これなら、ぜったいにひみつがばれないからあんしんだね。 3.個人関連情報(こじんかんれんじょうほう)ってなに? さいごはちょっとふしぎな「個人関連情報(こじんかんれんじょうほう)」! これはね、なまえやじゅうしょは書いてないんだけど、 たとえば… 「このタブレットをよくつかう人は、きっとようちえんの子だね」 「このあそびをよく見るのは、たぶんおとこのこかな?」 みたいに、ちょっとだけその人のことがわかっちゃうヒントがあるじょうほうのこと! だから、これもだいじにあつかわないといけないんだよ。 まとめるとこうなるよ! 名前 どんな情報? わかっちゃう? 仮名加工情報 名前などをちょっとかえたよ もしかしたらばれるかも? 匿名加工情報 だれかぜったいわからないようにしたよ ぜったいばれない! 個人関連情報 ヒントだけのこってるよ なんとなくわかるかも? おわりに みんなの「なまえ」や「あそびのこと」って、すごくたいせつなひみつなんだよ。 せんせいやおとなの人たちは、そのひみつをちゃんとまもるために、いろんなやりかたをつかってるんだ! だから、もしなにか聞かれたときは、「それってなんでつかうの?」って聞いてみてね。 みんなのひみつは、みんなのたからものだよ♥
-

2025.03.16
個人情報を加工して「個人情報」にも「匿名加工情報」にも該当しないケースとは?
個人情報の取り扱いは、企業にとって重要な課題の一つです。 特に、人材派遣会社や求人情報を扱う企業では、候補者の経歴やスキル情報を適切に管理し、必要に応じてクライアント企業へ提供する必要があります。 しかし、個人情報保護法の規制により、個人情報の取り扱いには厳格なルールが適用されます。 では、個人情報を加工した場合、どのようなケースで「個人情報」にも「匿名加工情報」にも該当しない状態になるのでしょうか?今回は、その条件と具体例について解説します。 1. 「個人情報」「匿名加工情報」とは? まず、「個人情報」と「匿名加工情報」の定義を整理しておきましょう。 個人情報(個人情報保護法 第2条第1項) 「特定の個人を識別できる情報」または「他の情報と照合することで識別できる情報」のこと。例えば、氏名、住所、生年月日、顔写真、社員番号などが該当します。 匿名加工情報(個人情報保護法 第2条第6項) 個人情報を加工し、「特定の個人を識別できないようにし、かつ元の情報に戻せないようにした情報」のこと。匿名加工情報として利用する場合、適切な管理が求められます。 つまり、単に名前を削除するだけでは「匿名加工情報」にはならず、ほかの情報(職歴、学歴、資格など)との組み合わせで特定可能であれば、引き続き「個人情報」として扱われます。 2. 「個人情報」にも「匿名加工情報」にも該当しないケースとは? では、どのように加工すれば、個人情報にも匿名加工情報にも該当しないのでしょうか?主に以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 個人が特定できないこと 個人情報であるかどうかの最大のポイントは、「特定の個人を識別できるかどうか」です。氏名や住所はもちろん、学歴や職歴、資格情報などを詳細に記載していると、他の情報と組み合わせることで個人が特定できる可能性があります。そのため、情報を抽象化し、個人識別性を排除する必要があります。 例: NG:「東京都〇〇区出身、〇〇大学卒、△△株式会社で営業経験5年」 OK:「都内の大学卒、営業経験あり」 ② 元の個人情報に復元できないこと 仮に匿名化した情報であっても、元のデータと照合して個人を特定できる場合、それは「仮名加工情報」や「個人情報」に該当する可能性があります。そのため、復元が不可能な形でデータを加工することが重要です。 例: NG:「Aさんの情報を基にした仮名の履歴書」 → 社内のデータと突き合わせれば特定可能 OK:「複数の経歴を統計的にまとめたデータ」 ③ 一般的な統計データや業界情報として利用できること 統計データや業界全体の情報のように、個人に紐づかない形でデータを整理すれば、それは「個人情報」にも「匿名加工情報」にも該当しません。 例: 「派遣登録者の平均年齢は35歳」 「ITエンジニア経験者のうち、80%がJavaスキルを持つ」 「営業職の平均勤続年数は5年」 このように、データを個別の情報から集計・統計化することで、個人識別性を排除することが可能です。 3. 具体的な活用例 ケース1:人材派遣会社がスキルデータを企業に提供する場合 人材派遣会社が企業に候補者の情報を提供する際、個人情報を伏せた形で「仮名の履歴書」を作成すると、社内データと照合すれば個人が特定できるため「個人情報」に該当する可能性があります。しかし、「〇〇分野の経験者が○○名在籍」といった統計的なデータに変換すれば、個人情報には該当しません。 例: NG:「Aさん(仮名):営業経験5年、英語ビジネスレベル」 OK:「営業経験5年以上の登録者:10名」 ケース2:マーケティングデータとして活用する場合 ある企業が顧客の購買データを分析し、マーケティングに活用する場合、個人の購買履歴をそのまま利用すると個人情報になります。 しかし、「20代男性の購入傾向」や「都内在住者の購買割合」などの統計データに変換すれば、個人情報には該当しません。 例: NG:「東京都〇〇区在住のAさんは、毎月〇〇を購入している」 OK:「東京都在住の30代男性のうち、〇〇を購入する割合は40%」 4. まとめ 個人情報を適切に加工することで、「個人情報」にも「匿名加工情報」にも該当しないデータとして活用することが可能です。 そのためには、以下のポイントを意識することが重要です。 ✅ 個人を特定できないように情報を抽象化する ✅ 他のデータと照合しても特定できないようにする ✅ 統計データや業界情報としてまとめる 企業がデータを活用する際は、個人情報保護法を遵守しながら、適切に情報を加工することが求められます。特に、人材派遣やマーケティングなどの分野では、データの取り扱いに細心の注意を払いながら、適切な方法で情報を活用していきましょう。
-

2025.03.03
AIモデル「Deep Seek」と個人情報
中国の企業DeepSeekが発表したAIモデルの「Deep Seek」は、低コストかつChatGPTに匹敵する高機能AIモデルとして今注目を浴びています。 しかしその使用について各国が警戒する動きを示しています。その大きな理由の一つが、個人情報の取扱い方です。 イタリアは、DeepSeek社が収集した個人情報をどのように取り扱うかについて情報を充分に開示していない点に懸念を示し、当該モデルの利用について差し止め命令を出しました。 韓国は、個人情報をどのように管理しているかをDeepSeek社に質問する計画を発表し、新規ダウンロードを停止させました。 フランスや、ベルギー、アイルランドでも、それぞれ調査に乗り出しています。 1. 日本における「Deep Seek」の取扱い方 では、日本は「Deep Seek」モデルについて、どのような見解を示しているのでしょうか? 以下、個人情報保護委員会H Pの一部を抜粋してみました。 (参考)https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/250203_alert_deepseek/ 生成AIサービスについては、その利用が世界的に普及している中、新たにDeep Seek社による生成AIサービスが開発され、サービス提供が開始されています。 同社の生成AIサービスについては、日本国内でサービス提供体制が構築されている他のサービスとは異なり、留意すべき点がありますが、同社が公表するプライバシーポリシーは中国語と英語表記のもののみとなっています。 このため、同社が公表するプライバシーポリシーの記載内容に関して、以下のとおり、情報提供を行います。 ①当該サービスの利用に伴いDeep Seek社が取得した個人情報を含むデータは、中華人民共和国に所在するサーバに保存されること ②当該データについては、中華人民共和国の法令が適用されること (参考) 上記②に関して、当該データに対しては、例えば以下のような法令が適用されることとなります。 中華人民共和国個人情報保護法 サイバーセキュリティ法 データセキュリティ法 中華人民共和国国家情報法 等 以上のように、日本では「Deep Seek」について、留意する点があるという姿勢を示すものの、まずはそのプライバシーポリシーの情報提供を行うことにとどまっています。 平将明デジタル相も「データ保護の観点で懸念が払拭されるまでは公務員が使うのは控えるか、使うのであれば留意すべきだ」と見解を述べています。 ところで、上記情報提供には、「Deep Seek」が日本の個人情報保護法とは異なった運用がなされることを示しています。 中国の個人情報保護法等は、安全保障上の目的によっては企業のデータを収集できるとされています。そのため、Deep Seek社が収集した個人情報が中国政府に取集される可能性も大いにありえます。 2. AIアプリと個人情報 以上のように「Deep Seek」と個人情報の関係についてみてきましたが、「Deep Seek」だけが懸念すべき対象であるというわけではありません。 今や、ChatGPTや「Deep Seek」に似たAIアプリが多数出回っている世の中です。 中には、本物そっくりの類似アプリ等もあり、注意が必要です。 類似アプリを使用してしまったら、最悪の場合、個人情報を不正に収集される可能性もあります。 AIアプリを使用する際はそのアプリが本物であるかどうか、また、プライバシーポリシーはどうなっているのかをしっかりとチェックし、見極めることが必要になってくるでしょう。
-

2025.02.07
外国と取引があってもプライバシーマークでGDPR対応が不要なケースとは?
こんにちは!今回は、「外国と取引がある場合でも、プライバシーマーク(Pマーク)上でGDPR対応が不要なケース」について解説します。 近年、個人情報保護の国際的な規制が強化され、**EU(欧州連合)の一般データ保護規則(GDPR)**もその代表的なものとして知られています。 日本国内では、プライバシーマークを取得している企業が増えていますが、「海外と取引がある場合、GDPR対応が必須なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 実は、外国と取引があるからといって、必ずしもGDPRに対応する必要があるわけではありません。 では、具体的にどのようなケースでGDPR対応が不要なのかを見ていきましょう。 1. GDPRが適用される企業の条件 まず、GDPRの適用範囲を確認しておきましょう。GDPRは、以下のいずれかに該当する企業に適用されます。 ✅ ① EU域内に拠点を持つ企業 日本企業であっても、EUに子会社・支店・営業所を持っている場合は、GDPRの対象になります。 ✅ ② EUに住む個人のデータを取り扱う企業 企業の所在地に関係なく、EU域内の個人データを処理する場合もGDPRの適用を受けます。具体的には、以下のような場合が該当します。 ・EU在住の顧客向けにWebサービスやECサイトを運営している ・EU居住者の個人情報を収集し、マーケティングに活用している ・EU企業の従業員情報を扱う業務を受託している 上記に該当する企業は、GDPR対応が必要になりますが、逆に言えば、この条件に当てはまらなければGDPR対応は不要となります。 2. GDPR対応が不要なケースとは? ケース①:外国企業との取引はあるが、個人データを扱わない 例えば、日本企業がアメリカやシンガポールの企業と取引をしている場合、企業間の取引(BtoB)であれば、GDPRの適用はありません。 企業情報(法人名、担当者名、連絡先)だけを交換している 個人データを取得・処理する業務がない このようなケースでは、GDPR対応をする必要はなく、Pマークの基準に従った個人情報管理を行っていれば問題ありません。 ケース②:EUと取引があるが、個人データを直接取り扱わない 次に、日本企業がEU企業と取引しているが、EU居住者の個人データを直接扱わない場合も、GDPR対応は不要です。 例えば、以下のようなケースです。 ✅ EU企業に製品や部品を納品するメーカー ✅ EU企業に対し、法人向けコンサルティングを提供している ✅ EU企業とBtoB契約を結んでいるが、従業員情報や顧客情報を取得しない このようなBtoB取引では、企業情報のみをやり取りするため、GDPRの対象外となります。 ケース③:EU在住者向けのサービスを提供していない GDPRは、「EU在住者をターゲットとするサービスを提供しているかどうか」も重要なポイントになります。 例えば、日本の企業が自社のWebサイトを運営していても、以下のような場合はGDPRの適用対象になりません。 ❌ EU向けの特別なマーケティングを行っていない ❌ Webサイトの言語が日本語のみで、EU在住者を想定していない ❌ EU居住者向けの商品販売やサービス提供を行っていない 👉 EUのユーザーを対象としない限り、GDPRの対応は不要です。 ケース④:データ処理を日本国内で完結している GDPRでは、「EU域内の個人データがEU外へ移転される場合」に厳しい規制を課しています。しかし、日本企業が扱うデータがすべて国内で完結している場合は、GDPR対応が不要です。 例えば、 ✅ 日本国内の顧客のデータのみを扱っている ✅ EU企業と取引しているが、データの保管・処理はすべて日本国内で行っている このようなケースでは、GDPRの規制を受けることなく、Pマークのガイドラインに沿った管理を行えば十分です。 3. プライバシーマークの基準を満たしていれば十分なケース Pマークは、日本の**JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)**の基準に基づいており、日本国内で適切な個人情報管理を行うための仕組みです。 GDPRとは異なるものの、Pマークの基準に従っていれば、日本国内の個人情報保護法(APPI)に準拠した管理ができるため、海外取引があっても問題にならないケースが多いのです。 特に、以下のような場合は、Pマークの運用を適切に行うことで十分対応可能です。 ✅ 外国と取引はあるが、個人情報を扱わない ✅ EUとの取引があるが、企業情報のみをやり取りしている ✅ 日本国内でデータ管理を完結させている これらのケースでは、GDPRの追加対応を行わなくても、Pマークの要件を満たしていれば問題なしと考えられます。 4. まとめ:GDPR対応が不要なケースを把握しよう! 「外国と取引があるからGDPR対応が必須」というわけではありません。GDPRの適用条件を理解し、自社が本当に対応が必要なのかを見極めることが重要です。 🔹 GDPR対応が不要なケース✅ BtoB取引で、個人情報を取り扱わない ✅ EU企業と取引はあるが、EU居住者のデータを処理しない ✅ EU向けのサービス提供やマーケティングを行っていない ✅ データ処理をすべて日本国内で完結させている Pマークを取得している企業は、すでに個人情報管理の基盤が整っているため、上記のようなケースでは、特別なGDPR対応を行う必要はありません。 👉 「自社にGDPR対応が本当に必要なのか?」をしっかりと判断し、適切な個人情報保護体制を整えていきましょう!
-

2025.02.07
プライバシーマークとGDPR対応:企業が求められるポイントとは?
こんにちは!今回は、プライバシーマーク(Pマーク)取得企業が対応すべき「GDPR(一般データ保護規則)」の要件について解説します。 近年、個人情報の取り扱いに関する法規制が世界的に厳しくなっています。日本国内での個人情報保護の認証制度であるプライバシーマークと、EU(欧州連合)が定める**GDPR(General Data Protection Regulation)**には、どのような関係があるのでしょうか?また、Pマークを取得している企業は、GDPRにどのように対応すればよいのでしょうか? 1. プライバシーマークとGDPRの関係とは? プライバシーマークは、日本国内のJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)の基準に基づき、企業の個人情報管理の適切性を認証する制度です。一方、GDPRはEU域内の個人データ保護を目的とした法規制であり、日本の個人情報保護法(APPI)よりも厳格な基準を設けています。 プライバシーマーク取得企業でも、GDPRの適用対象となる場合があるため、追加の対応が必要となるケースがあります。 2. GDPRが適用される企業とは? GDPRは、以下のような企業に適用されます。 ✅ ① EU域内に拠点を持つ企業 日本企業であっても、EUに現地法人や支店を持っている場合、GDPRの適用を受けます。 ✅ ② EU域内の個人データを扱う企業 たとえば、以下のようなケースでは、GDPRの適用対象となる可能性があります。 ・EUに住むユーザー向けのWebサービスを提供している(ECサイト、会員制サービスなど) ・EU居住者の個人データを収集し、マーケティングに活用している ・EU企業との取引で、EU居住者の個人データを扱っている GDPRでは、企業の所在地に関係なく、EU域内の個人データを取り扱う場合は適用対象になるため、海外ビジネスを展開している日本企業も無関係ではありません。 3. プライバシーマーク取得企業が求められるGDPR対応 Pマークを取得している企業は、すでに個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を整備しているため、GDPRの基本要件を満たす土台はできています。しかし、GDPRの追加要件を満たすためには、以下の対応が必要です。 ✅ ① 「適法な処理(Lawfulness of Processing)」の要件確認 GDPRでは、個人データを処理するには、明確な法的根拠が必要です。特に重要なのは、以下の6つの適法根拠です。 ・データ主体の同意(Consent) ・契約履行のために必要(Contract) ・法的義務の履行(Legal Obligation) ・データ主体の重大な利益保護(Vital Interests) ・公的機関の業務(Public Task) ・正当な利益(Legitimate Interests) Pマークでは「本人の同意」を重視しますが、GDPRでは「契約履行」や「正当な利益」も適法根拠として認められます。そのため、データ収集の目的と法的根拠を明確に整理することが求められます。 ✅ ② データ主体の権利対応(データアクセス権・削除権など) GDPRでは、個人データを保有する企業に対し、データ主体(個人)が次の権利を行使できることを求めています。 ・アクセス権(自身のデータがどう利用されているか確認する権利) ・訂正権(誤ったデータを修正する権利) ・削除権(忘れられる権利)(データの削除を要求する権利) ・データポータビリティ権(他のサービスにデータを移転する権利) Pマークの運用だけではGDPRのこれらの要件を完全に満たせない場合があるため、データ主体からの請求に対応できる体制を整える必要があります。 ✅ ③ データ処理契約(DPA)の締結 GDPRでは、個人データを第三者に提供する際、**データ処理契約(Data Processing Agreement: DPA)**を締結し、データの取り扱いを明確に定める必要があります。 Pマークでは「委託先管理」が求められますが、GDPRではより詳細な契約書の取り決めが求められるため、EU企業との取引がある場合は契約内容を見直す必要があります。 ✅ ④ 個人データの海外移転への対応 GDPRでは、EU域内から第三国(EU外)への個人データ移転について厳格な規制があります。日本は「十分性認定(Adequacy Decision)」を受けているため、基本的にはEUから日本へのデータ移転は認められていますが、適切なデータ保護措置を講じていることを証明することが求められます。 Pマーク取得企業は、日本国内基準でのデータ保護は整備されていますが、GDPRの要件も考慮したデータ移転ポリシーの策定が必要です。 4. まとめ:Pマーク取得企業もGDPR対応を意識しよう! プライバシーマークを取得している企業は、すでに個人情報の管理体制を整えているため、GDPR対応の基盤はできています。しかし、GDPRは日本の個人情報保護法よりも厳格なルールを求めるため、追加対応が必要です。 特に、海外ビジネスを展開している企業や、EU域内の個人データを取り扱う企業は、以下のポイントを意識しましょう。 ✅ 適法なデータ処理の根拠を明確にする ✅ データ主体の権利行使に対応できる体制を整える ✅ データ処理契約(DPA)を適切に締結する ✅ 海外移転ルールを理解し、適正なデータ管理を行う GDPR対応を進めることで、グローバル基準の個人情報保護体制を確立し、企業の信頼性を向上させることができます! 今後も、データ保護の国際基準を意識した個人情報管理を進めていきましょう!
お問い合わせ
営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日
事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能